FXの自動売買(EA)に興味はあるけれど、仕組みや始め方、注意点が分からない——そんな初心者向けの入門ガイドです。EAと裁量の違い、EAがどう動き何が得意・不得意か、良いEAの見極め方(成績・リスク・コスト)、MT4/MT5設定やバックテスト・デモ・VPSまでの手順、資金管理とドローダウン対策、過剰最適化や詐欺の回避法を、数字と具体例でやさしく解説します。
- そもそもEA(自動売買)って何?FXの裁量取引とどう違うの?
- EAはどんな仕組みで動き、どんな相場で得意・不得意があるの?
- EAは何を見てどう判断するのか(内部の流れ)
- 手法別に見る「得意な相場」「苦手な相場」
- 相場判定フィルターの作り方
- うまくいかない場面の典型と回避策
- テストと検証で見落としやすいポイント
- 実運用の始め方ミニガイド
- 通貨ペア・時間帯の相性と実務のコツ
- まとめ:EAの仕組みを理解して、相場ごとに役割分担を
- 初心者がEAを選ぶとき、実績・リスク・コストはどう見分ければいいの?
- まず押さえるべき「3つの物差し」
- 実績の見方:魅力的な曲線に騙されない
- リスクの見方:破綻確率を先に潰す
- コストの見方:スプレッドより「総摩擦」
- 手法ごとの落とし穴を事前に嗅ぎ分ける
- 比較・選定の実務フロー
- 数値で並べる簡易スコアリング例
- 赤信号・黄信号のサイン集
- 資金配分とポートフォリオの考え方
- 結論:買う前に試算、走らせながら逸脱を検知
- 導入と運用はどう始める?MT4/MT5の設定、バックテスト、デモ運用、VPSは必要?
- どんなリスク管理と注意点が必要?資金管理、ドローダウン、過剰最適化や詐欺をどう避ける?
- 最後に
そもそもEA(自動売買)って何?FXの裁量取引とどう違うの?
EA(自動売買)とは?
EAは「Expert Advisor」の略で、定義された取引ルールに従って注文・決済・損益管理を自動で行うプログラムです。
人の判断や感情を介さず、相場の監視から発注、リスク管理までを機械的に実行します。
代表的にはMT4/MT5上で動くMQL4/MQL5製のEAが知られていますが、cTraderや独自APIで動くボットもあります。
たとえば「移動平均線のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで手仕舞い」「ロンドン時間のブレイクでエントリーし、ATRの2倍で損切り」といったルールをコード化して、24時間マーケットを監視。
条件が揃えば即座に発注し、設定どおりに損切り・利確・トレイリングストップを行います。
人間が画面に張り付く必要はありません。
EAが動く仕組みの基本構成
- データ入力:ブローカーが配信する価格やティック、足データ(1分足など)を取得
- シグナル生成:テクニカル指標や価格アクションの条件で「買い/売り/見送り」を判断
- 執行:成行・指値・逆指値などの注文を即時に送信、スリッページや部分約定に対応
- リスク管理:ロット、損切り・利確、分割決済、トレイリング、最大ドローダウン制限
- 運用環境:常時稼働のPCやVPS、安定した回線、適切なブローカー環境
完全自動と半自動(セミオート)
EAには、すべてを任せる完全自動と、エントリーのみ手動・決済だけ自動などの半自動もあります。
重要イベント前だけ停止する、複数EAを時間帯で切り替えるなど、柔軟な運用設計が可能です。
裁量取引とは?
EAとの違い
裁量取引は、チャート分析・ニュース・経験則などをもとに、人が状況に応じて判断し注文を出す取引です。
EAとの主な違いは以下の通りです。
- 判断主体:EAはルール固定。裁量は相場状況に応じて人が判断を上書きできる
- スピード:EAはミリ秒単位の実行が可能。裁量は認知・判断・クリックの遅延がある
- 再現性:EAは同じ条件で同じ結果。裁量は日によって判断がぶれることがある
- 柔軟性:裁量は突発ニュースや板気配を加味しやすい。EAは事前ルール外に弱い
- 感情の影響:EAは恐怖・欲に左右されない。裁量はメンタル管理が勝敗を左右
- 運用時間:EAは24時間監視可能。裁量は時間的制約を受けやすい
同じ相場で起きる具体的な違い
たとえば雇用統計直後の急変動。
EAは「ボラティリティ閾値超過で取引停止」と設定していれば機械的に様子見。
一方、裁量なら板の薄さやニュース本文を見て「一瞬の逆張り」や「方向確定後の押し目買い」を選べます。
逆に、深夜の小動きの中でのレンジ逆張りなどはEAのほうが疲れ知らずで淡々と実行できます。
EAのメリット
- 感情を排し、ルールに忠実な執行ができる
- 24時間の監視・高速執行で、チャンスを取りこぼしにくい
- バックテスト・フォワードテストで戦略の再現性を検証しやすい
- 複数通貨ペア・戦略の同時運用で分散しやすい
- 定量的な改善サイクル(データ→仮説→検証→改良)が作りやすい
EAのデメリット・注意点
- カーブフィッティング(過剰最適化)の罠:過去にだけ強い設定は将来に弱い
- 想定外イベントに弱い:ルール外の事象や配信停止、極端なスプレッド拡大
- ブローカー依存:約定力、レイテンシ、約定仕様で成績が変わる
- メンテナンス負荷:VPS、プラットフォーム更新、データ欠損対応
- コスト:スプレッド/手数料/スリッページが積み上がると戦略優位性が消える
盲点になりやすい運用リスク
- スプレッドと時間帯特性:指標前後やロールオーバーで拡大しやすい
- スリッページ:高速相場ではエントリー・エグジットともに滑る前提で設計
- 価格フィードの品質:ティック欠損や異常値で誤発注が起きることがある
- VPSと回線安定性:一時停止で予定の損切りが執行されないリスク
- 最大ドローダウン:統計的に想定した下振れの「さらに外側」が必ず起こり得る
裁量取引のメリット・デメリット
メリット
- ニュースや板、センチメントなど定量化しにくい情報を統合できる
- ボラ急拡大・薄商いなど、危険地帯を直感的に回避しやすい
- 相場の地合い変化に合わせてルール自体を柔軟に変更できる
デメリット
- 感情に左右されやすく、一貫性の維持が難しい
- 監視時間と体力の制約で機会損失が生じやすい
- 記録・検証が甘くなると、改善サイクルが回らない
EAと裁量、どちらが向いている?
- 規律重視・データで改善したい・長時間の監視が難しいならEA向き
- ニュース理解や地合いの読みが得意・臨機応変に対応したいなら裁量向き
- 両立策:裁量で相場観を磨きつつ、得意パターンをEA化して再現性を上げる
「EAは放置で儲かる」は誤解
EAは「勝てるロジック」「適切なリスク管理」「整った運用環境」の3点が揃って初めて機能します。
市場は常に変化し、優位性は劣化します。
バックテストで良くても、フォワードで同様になる保証はありません。
放置よりも「モニタリングと必要最低限のチューニング」を前提に考えましょう。
成果を左右する3つの鍵
1. 戦略の優位性
- シンプルな原理に基づくこと(トレンドフォロー、ブレイク、ミーンリバージョンなど)
- 複数通貨・期間でのロバスト性(パラメータが大きく変わっても崩れにくい)
- 過去の異常局面(フラッシュクラッシュ、パンデミック時)を含むテスト
2. リスク管理
- ロット固定よりリスク一定(口座残高の一定%)を基本に
- 最大ドローダウン許容の事前定義(到達時は停止・縮小)
- ポジション分散(通貨・手法・時間帯の相関を下げる)
- ナンピン/マーチンは最大損失を明確に。上限なしは避ける
3. 運用環境
- 安定稼働のVPS(低レイテンシ、電源・回線冗長)
- 約定力と透明性の高いブローカー(スプレッド・手数料・約定方式を確認)
- 定期的なログ確認とアラート通知(異常停止や連続損失の早期察知)
バックテストとフォワードテストの使い分け
バックテストは過去のデータで戦略の骨格を検証する工程。
ここでの目的は「勝つことの証明」ではなく「致命的な欠陥の早期発見」です。
次にデモ口座や極小ロットでフォワードテスト。
スリッページ、スプレッド拡大、約定遅延など、実運用の摩擦コストを加味したうえで初めて評価が固まります。
最適化は最小限に留め、期間外データでの外部検証を行うと過剰最適化を避けやすくなります。
代表的なEA手法とリスクの勘所
- トレンドフォロー:大きな波に乗る。勝率は低めでも損小利大が成立しやすい
- ブレイクアウト:レンジ離れを狙う。ダマシ回避のフィルター設計が要
- ミーンリバージョン(逆張り):勝率高めだが一撃の損が大きくなりやすい
- グリッド/ナンピン:レンジで強いがトレンドで破綻しやすい。上限と撤退ルール必須
- ニュース回避型:指標前後に停止。イベントリスクを外しつつ地合いに追随
コストと約定の現実を織り込む
スプレッド0.2pips縮小は、短期EAにとって日々の期待値を大きく押し上げます。
逆にスリッページ±0.3pipsの常態化は優位性を消します。
バックテストで手数料・スリッページを厳しめに設定し、ロールオーバー時間や週明けギャップの取り扱いも明確にしましょう。
EAと裁量のハイブリッド運用
- 時間帯フィルター:流動性の低い時間帯だけEA停止、ロンドン・NYだけ稼働
- ニュースフィルター:重要指標・要人発言前後は裁量で停止・再開を管理
- ヘッジ分散:EAはトレンド系、裁量は逆張り短期など相関を下げる組合せ
- 裁量で得意パターンを抽出し、EA化して再現性を高める
よくある疑問と答え
Q. EAだけで安定して勝てる?
A. 可能性はありますが、相場環境の変化で優位性は劣化します。
定期的な検証と縮小・停止の判断が不可欠です。
Q. どの通貨ペアが有利?
A. 手法によります。
トレンド系はボラティリティの高い通貨、逆張りはレンジ傾向の通貨が相性良いことが多いですが、必ずデータで確認しましょう。
Q. 複数EAの同時運用は?
A. 相関の低い手法と通貨の組み合わせが前提。
リスクの合算(同時にドローダウンしないか)を管理すべきです。
実運用に入る前のチェックリスト
- バックテストは複数期間・複数通貨で実施し、外部検証を含むか
- スプレッド・手数料・スリッページを厳しめに設定しても優位性が残るか
- 最大連敗・最大ドローダウンを想定し、口座資金とロットが妥当か
- 停止ルール(損失閾値・相場条件)と再開条件を明文化しているか
- VPS・回線・ブローカーの運用体制が整っているか
まとめ:EAは「規律と再現性」、裁量は「柔軟性と適応力」
EA(自動売買)は、明確なルールを高速・正確に執行することで、規律と再現性をもたらします。
対して裁量取引は、相場の地合いやニュース、板の雰囲気といった非定量の情報を取り込んで柔軟に適応できます。
どちらが優れているかではなく、目的・強み・ライフスタイルに合わせて選ぶ、あるいは組み合わせるのが賢明です。
重要なのは、どのアプローチでも「リスク管理を中心に据える」こと。
期待値の源泉(戦略の優位性)を守り、摩擦コスト(スプレッド・スリッページ)を最小化し、想定外の下振れに備える設計を徹底しましょう。
EAは魔法ではありませんが、正しく設計・検証・運用すれば、取引をより安定的で持続可能なものへと近づけてくれます。
EAはどんな仕組みで動き、どんな相場で得意・不得意があるの?
EAの動作原理と相場適性をプロが解説:仕組み・強み・弱みを具体例で理解する
EA(Expert Advisor)は、取引プラットフォームに接続して、定義されたルールに従い自動で売買を行うプログラムです。
人の感情に左右されず、決めた条件を何度でも正確に繰り返せるのが特徴です。
ただし、どのEAにも「得意な相場」と「苦手な相場」があり、それをわかって使い分けることが勝率を大きく左右します。
ここでは、EAがどのように意思決定しているのか、そして手法ごとの相性の良い相場・悪い相場を実践目線で整理します。
EAは何を見てどう判断するのか(内部の流れ)
EAの基本的なサイクルは、価格や板情報の受信→ルール判断→発注→ポジション管理→決済という流れです。
多くのEAは「ティック」や「バーが確定したタイミング」で次の処理を走らせ、過去データと現在の価格を見比べて売買の可否を判断します。
主な構成要素は以下のとおりです。
シグナル生成の考え方とよく使う材料
- 価格と移動平均線:ゴールデンクロス/デッドクロス、MAの傾き、価格の乖離
- オシレーター:RSIの過熱/売られすぎ、ストキャスのクロス、CCIのゼロライン復帰
- ボラティリティ系:ATRでの損切幅計算、ボリンジャーバンドの収縮/拡大
- 価格パターン:高値・安値の更新(ブレイク)、サポレジ反転
- 時間・イベント:ロンドン/NYのオープン、経済指標前後のフィルタ
これらを組み合わせ、「どの条件が揃えば買い、どの条件で見送り、どの条件で手仕舞い」という論理を明文化します。
エントリーとエグジットのルール設計
エントリーは「成行」「指値(リミット)」「逆指値(ストップ)」のいずれかを使います。
トレンドフォローは逆指値で高値更新に追随、レンジ狙いは指値で押し目・戻り目を待つなど、手法に応じて最適な執行方法が異なります。
決済では、固定TP/SL、ATR連動の可変幅、トレーリング、分割利確、ブレークイーブン(建値ストップ)などを組み合わせ、勝ちの伸ばし方と負けの限定をバランスさせます。
ポジションサイズと資金管理の自動化
EAの強みはリスク量を機械的に一定化できる点です。
たとえば「1トレードの損失を口座残高の1%に制限」「ATR×nを損切幅にしてロットを逆算」など。
連敗時はロットを自動縮小する、日次の損失上限で取引停止するなどのルールを入れると、想定外のドローダウンを抑えやすくなります。
実行環境と約定のリアル(VPS・スプレッド・滑り)
EAは回線・約定品質に敏感です。
少しの遅延やスプレッド拡大は特に短期手法の成績を大きく変えます。
VPSで24時間稼働、指標時のスプレッド拡大を検知して一時停止、最小ストップ距離や最小ロットなどブローカー仕様の制限を考慮するなど、環境面の設計も勝ち負けを分けます。
手法別に見る「得意な相場」「苦手な相場」
トレンドフォロー型
特徴:高値・安値の更新に乗る、移動平均の傾きやADX上昇で追随。
得意:強い方向性が続く相場(例:金融政策の方向が明確で、押し目が浅い局面)。
苦手:方向感のないボラティリティ縮小、ダマシの多い小刻みな反転。
注意点:ブレイク直後はスプレッド拡大・スリッページで不利約定になりやすい。
フィルタとして「直近の値幅(ATR)」や「時間帯(ロンドン開始後)」を組み合わせるとダマシ回避に有効です。
レンジ回帰(ミーンリバーション)型
特徴:オシレーターの極端値やボリンジャー外側タッチから中心回帰を狙う。
得意:方向性が弱く、上下に往復しやすい膠着相場(東京午前など)。
苦手:トレンドの初動やニュースでバンドウォークが続く局面。
注意点:逆行が伸びると損切りが大きくなりやすいので、回数で勝つ前提の小さめTP/タイトSL、時間切れ決済、最大連続ポジション数の制限が鍵です。
ブレイクアウト/ボラティリティ拡大狙い
特徴:一定時間の高安レンジを上抜け/下抜けでエントリー。
得意:ロンドン勢参入や重要指標でレンジが崩れてトレンドが走る日。
苦手:レンジブレイクの「すぐ戻る」ダマシや、抜けても伸びない日。
注意点:直前のレンジ幅が狭すぎる場合は見送り、1回目が失敗したら再突入は回避するなど、再エントリー制御が有効です。
スキャルピング型
特徴:数pips〜十数pipsを多数回で積む超短期。
得意:スプレッドが安定して狭く、板が厚い時間帯(主にロンドン〜NY序盤)。
苦手:指標前後や早朝の流動性薄くスプレッド拡大時、週明け・週末のギャップ。
注意点:実コスト(スプレッド+手数料+滑り)がすべて。
バックテストではコストを厚めに上乗せし、現実を織り込むことが必須です。
グリッド/ナンピン系
特徴:一定間隔で買い下がり・売り上がり、平均建値を有利化して反発で利確。
得意:レンジが続いて小刻みな往復が起きる相場。
苦手:片方向の持続トレンド、政策変更や地政学で急伸・急落が長引く局面。
注意点:含み損の雪だるま化を防ぐため、最大ポジション数や強制損切りの「破綻防止ルール」を最優先で設計。
スワップ方向も必ず確認します。
ニュース・時間帯依存型
特徴:経済指標や市場オープン前後のパターンに特化。
得意:季節性・時間帯の一貫性があるパターン(例:ロンドンオープンのボラ拡大)。
苦手:予定外ニュースでパターンが壊れる日、発表直後の極端なスリッページ。
注意点:直前停止と再開のタイマー管理、スプレッド上限フィルタ、約定拒否・価格乖離の例外処理を丁寧に。
相場判定フィルターの作り方
同じEAでも、状況に合ったフィルターを入れるだけで成績が別物になります。
以下のような基準でオン/オフやロット調整を行うと、苦手相場の露出を減らせます。
ボラティリティで切り替える
- ATRが一定以上ならトレンド系を優先、一定未満ならミーンリバーション系に切替
- ボリンジャーバンド幅の拡大/縮小率でブレイク狙いの許可・不許可を制御
- スプレッドが閾値を超えたらエントリー禁止(特に短期手法で有効)
トレンド強度で切り替える
- ADXや移動平均の傾き(複数時間軸の合意)で順張りのみ許可
- 直近高安の更新回数、ローソク実体の連続性をスコア化して判定
- 上位足(例:4H/日足)が横ばいの時は逆張りのみ稼働
時間・セッションで振り分ける
- 東京時間は逆張り寄り、ロンドン〜NY序盤はブレイク・順張り寄り
- 週明け直後・週末クローズ前は新規禁止、金曜は保有時間制限
- 重要指標カレンダー連動で前後X分は停止、またはロット縮小
うまくいかない場面の典型と回避策
レジームチェンジ(相場の性質が切り替わる)
長期のレンジが続いたあと突然トレンドが走る、あるいはその逆。
EAは過去の平均的条件に合わせているため、変化点で連敗しがちです。
複数手法のポートフォリオ化、フィルターで「むしろ変化点を検出」して手仕舞い・停止する仕組みを入れるとダメージを軽減できます。
流動性低下とスプレッド拡大
指標直前、早朝、祝日などはスプレッドが急拡大し、成績が崩れます。
EA側に「スプレッドが閾値を超えたら新規禁止」「滑り許容幅を制限」「指値・逆指値の再設定ロジック」を持たせ、危険な時間帯を避けることが現実解です。
連敗ドローダウンの深掘れ
手法に必ず「負けの並び」は存在します。
許容想定を超えるとロット縮小や自動停止が必要です。
推奨は、最大ドローダウンの想定をバックテストよりも2〜3割厳しく見積もり、日次・週次で損失上限を超えたら一旦クールダウンするルールを機械化することです。
テストと検証で見落としやすいポイント
データ過剰最適化を避ける
インジケーターの期間や利確幅を細かく最適化しすぎると、過去にだけ強い戦略になってしまいます。
期間をずらしても成績が大崩れしないか、年度別・相場環境別に均して勝てているか、未知の期間(アウト・オブ・サンプル)での再現性を確認しましょう。
ウォークフォワードやモンテカルロで頑健性を検証する視点が有効です。
スプレッド・手数料・スリッページの上乗せ
バックテストでは実コストを「多め」に見積もります。
スキャルならスプレッド+0.2〜0.5pips、スイングでもニュース時の滑りを想定。
最小ストップ距離や最小ロットなどブローカー仕様も事前に反映させ、テストと実運用の差を小さくします。
スワップ/ロールオーバーの影響
保有期間が長い戦略はスワップポイントの積み上がりが成績を動かします。
通貨ペアの金利差や週末の3日付与、月末・期末の特異点もチェック。
スワップが不利な方向の長期保有を避けるため、最大保有時間や決済優先ルールを入れておくと安定します。
実運用の始め方ミニガイド
小さく始める手順
- デモ口座で最低1〜2カ月、相場イベント(指標・要人発言)を跨いで挙動確認
- リアルの最小ロットで開始し、月次の最大ドローダウンが想定内なら段階的にロットを増やす
- VPSを導入し、再起動・回線断時の再稼働チェック(自動ログイン・再起動後の復帰)
- 複数EAの同時運用時は、相関の高い通貨・手法が同時に負けないよう、時間帯や通貨で分散
監視すべき指標
- 損益曲線の傾きと最大ドローダウン(資金曲線が水平化・右下がりになったら一時停止)
- 勝率・プロフィットファクター・平均RRの変化(手法の性質に合っているか)
- 約定品質(平均滑り・拒否率・スプレッド実績)
- ニュースカレンダー(CPI、雇用統計、FOMCなどは原則停止かロット縮小)
通貨ペア・時間帯の相性と実務のコツ
欧州系(EURUSD、GBPUSD)はロンドン時間のトレンドフォローが機能しやすく、USDJPYは東京〜ロンドンの切り替わりで回帰・短期順張りの両方が狙えます。
XAUUSDは瞬間的なスプレッド拡大や滑りが大きい一方、ボラ拡大局面ではブレイクが強く出ます。
EA側には「通貨ごとの最小TP/SL」「ボラ連動ロット」「時間帯稼働スケジュール」を持たせると相性が上がります。
まとめ:EAの仕組みを理解して、相場ごとに役割分担を
EAは、価格データを入力にルールで意思決定し、機械的なリスク管理と発注を行うプログラムです。
勝ち続けるカギは「どの手法がどの相場で強いか」を把握し、環境認識フィルターと資金管理で苦手相場への露出を減らすこと。
トレンドには順張り、膠着には回帰、ボラ拡大にはブレイク、短期にはスキャル、往復にはグリッドと、役割を分けて運用するのが実践的です。
検証では過剰最適化を避け、実コストを厚く見積もる。
運用では小さく始め、停止条件と再開ルールを明確に。
EAは「感情を排した再現性」を提供しますが、相場の変化に合わせた取捨選択とメンテナンスが、長く使える武器に育てる最短ルートです。
初心者がEAを選ぶとき、実績・リスク・コストはどう見分ければいいの?
EA選びの核心:実績・リスク・コストを数字で見極める現場のチェック法
「どのEAが良いのか」を感覚で決めると、たまたまうまくいった相場の切り抜きや美しい曲線に引っ張られがちです。
必要なのは、実績・リスク・コストを同じ物差しで並べて判断すること。
ここでは、現場で実際に使っているチェック観点と、購入前から小額運用までの手順を、数字で比較できる形に落とし込みます。
まず押さえるべき「3つの物差し」
EAを評価する際の土台は次の3つです。
- 実績(Performance):結果がどれくらい再現性高く出ているか
- リスク(Risk):資金曲線の沈み方がどの程度まで想定されるか
- コスト(Cost):約定の摩擦や維持費を含め、実益をどれだけ削るか
それぞれを個別に良く見せるのは簡単ですが、3つを同時に満たすEAだけが長く口座を守ります。
以下で、具体的指標と目安を示します。
実績の見方:魅力的な曲線に騙されない
公開成績の信頼性を確認するチェックポイント
- 第三者サイトの検証済みか(Myfxbook/FX BlueのTrack Record・Trading PrivilegesがVerified)
- 実弾口座かデモか(実弾の方が摩擦の影響が反映されやすい)
- 運用期間の長さ(最低でも実運用6〜12カ月、できれば複数の相場局面を跨いでいる)
- 取引回数・サンプル数(戦略にもよるが200〜500トレード以上あると統計が安定)
- 入出金の頻度(入金で曲線を持ち上げていないか、出金でドローダウンを隠していないか)
- ブローカーと口座タイプ(ECN/手数料型か、固定/変動スプレッドか、スリッページ耐性)
- エクイティ曲線と残高曲線の乖離(含み損を抱えていないか)
成績の質を測る主要指標
- 勝率と平均損益比(R):R=平均利確/平均損失。勝率が低くてもRが高ければ期待値はプラスになりうる。
- 期待値(Expectancy):勝率×平均利確 − 敗率×平均損失。1トレードあたりの平均利益。
- プロフィットファクター(PF):総利益/総損失。1.3〜1.6は良好、2.0以上は優秀だが過剰最適化に注意。
- 最大ドローダウン(Max DD):資金曲線の最大落ち込み。%で必ず把握する。
- リカバリーファクター(RF):総利益/最大DD。1.5以上で健全、2.0以上で強い。
- 停滞期間(Stagnation):過去最高値更新までに要した日数。長いほど心理的耐性が必要。
- 平均保有時間と曜日・時間帯の偏り:実際の約定摩擦やニュース影響を推測しやすい。
最低限クリアしたい目安
- 実運用またはリアルに近い環境で6カ月以上の履歴
- PF 1.3以上、最大DD 25%以下、RF 1.5以上
- 取引回数200以上(スイングなら100以上でも可)
- エクイティと残高の乖離が小さい(含み損の先送りがない)
カーブフィッティングの兆候
- パラメータがやたら多い、時間帯フィルターや通貨フィルターが過剰
- バックテストは完璧だが実運用ではPFやDDが劣化
- 短期間で急勾配の資金曲線(特定相場への依存)
- 取引頻度が極端に低いのに成績が突出(偶然当たりの可能性)
リスクの見方:破綻確率を先に潰す
戦略内蔵のリスクを言語化する
- 損切りの明確さ:固定SLか、ボラ連動か、なし(資金拘束や破綻リスク大)か
- 増し玉の有無:ナンピン・マーチン・グリッドは見返りの代わりに尾リスクが急増
- 同時保有数上限:相関ポジションの積み上がりで有効証拠金を圧迫しないか
- ニュース・週末跨ぎ:ギャップや急変でSL滑りの想定があるか
- 平均保有時間:短期は摩擦に弱い、長期はスワップやイベントリスクに晒される
想定ドローダウンと資金計画
最大DDの「期待値」と「最悪ケース」を分けて考えます。
例えば、バックテストで最大DDが20%のEAを、そのまま実運用に当てはめるのは危険です。
実運用ではスリッページやデータの穴、レジームチェンジがあるため、1.5〜2倍程度を最悪ケースとして見積もるのが現実的です。
- 例:最大DD(BT)20% → 想定DD(実運用)30〜40%
- 許容DD(口座全体)を20%にしたいなら、そのEAの配分を下げるか、ロットを減らす
ポジションサイズの安全域
- 1トレードの口座リスクは0.5〜1.0%を上限に設計
- 同時保有上限を考慮した「最悪同時損切り時の総リスク」を2〜3%以内に抑える
- 証拠金使用率は30%以下、含み損が広がるグリッド系は20%以下を目安
停止・減量ルール例
- 直近90日DDが過去最大DDの70%に接近でロット半減、80%で停止
- 停滞期間が過去最長を更新し、PFが1.0割れで停止
- スプレッド拡大・約定品質悪化(平均スリッページが3倍化)が2週継続で停止
コストの見方:スプレッドより「総摩擦」
総コスト=スプレッド+手数料+スリッページ+スワップ+運用費
コストは1回の往復取引あたりの「pips換算」で把握します。
- スプレッド:例)EURUSD 0.8pips
- 手数料:$7/lotを0.7pips相当と換算(およそ1pips≒$10/lot目安)
- スリッページ:平均0.3pips
- スワップ:保有平均12時間で−0.1pips相当
- VPS/ツール費:月額を月間取引回数で割ってpips換算
例)合計=0.8+0.7+0.3+0.1=1.9pips。
TAKEが平均3.0pipsのスキャルなら、摩擦後の純利益余地は1.1pipsしかありません。
数字で見ると、どのEAがコスト耐性に優れるかが一目瞭然になります。
ブローカー選定の現実
- ロンドン・NY時間の実測スプレッドと滑りを重視(アジア時間は薄い)
- 約定速度(ms)とリクオート率、VPS設置場所(ブローカーの近接)
- スワップ条件の安定性(突然の改定は戦略崩壊に直結)
損益分岐の計算
損益比Rが1.5、総コスト1.5pips、平均損切り10pips、平均利確15pipsなら、コスト後の実効Rは(15−1.5)/(10+1.5)≒1.17。
損益分岐の勝率は1/(1+R)≒46%。
この勝率を過去実績が十分に上回っているかを確認します。
手法ごとの落とし穴を事前に嗅ぎ分ける
スキャル型
摩擦に極端に弱い。
スプレッドと滑りが1pips悪化するとPFが一気に1を割ることも。
小利大損に傾く設計(広いSL・狭いTP)は要注意。
実運用の約定ログで摩擦を毎週点検すること。
トレンドフォロー型
勝率は低めでもRが高い。
停滞期間が長くなりやすいので、資金管理と精神面の耐性が鍵。
指標急変で滑る前提のSL余裕が必要。
レンジ回帰型
平常時は安定、トレンド相場で連敗や踏み上げが発生。
ボラティリティ拡大時のフィルターや最大連敗想定を持つこと。
グリッド・ナンピン・マーチン
含み損を抱えやすく、エクイティと残高が乖離。
普段は高勝率・滑らかな曲線だが、レジーム変化で一撃DDが深くなる。
証拠金使用率管理と強制ロスカットラインの事前把握が必須。
比較・選定の実務フロー
10分スクリーニング
- 公開成績の検証バッジ(Verified)と実弾確認
- PF・DD・RFの三点セット、取引回数、期間
- 戦略タイプ(スキャル/スイング/グリッドなど)とSLの有無
- 保有時間と稼働セッションの整合性(コストと噛み合うか)
1時間の深掘り
- 月別成績のブレ、停滞期間、連敗の深さ
- 通貨ペア別の偏り、相関の強さ(同種EAを同時に入れない)
- バックテストの期間・品質(スプレッド上乗せ、スリッページ設定の有無)
- 設定項目の多さ(調整自由度が高すぎる=カーブフィットの余地が大)
- 販売者の更新頻度・サポート体制(相場変化への追随力)
小額フォワード運用
- 同一ブローカー・同一口座タイプ・VPSで、最小ロットから開始
- 2〜4週間の実測で「総摩擦pips」「実効PF」「滑り分布」を取得
- 停止・減量ルールを先に設定(到達したら迷わず実行)
- 口座全体リスクは分散(1EAあたり資金の20〜30%まで)
数値で並べる簡易スコアリング例
- 実績(40点):PF・RF・DD・停滞期間を総合。PF1.5以上+DD20%以下+RF2.0以上で満点近く。
- リスク(40点):SL明確+ノーナンピン+同時保有限+証拠金余力の設計で高得点。
- コスト(20点):総摩擦pipsが戦略の平均利確の50%未満なら満点。実測ログ優先。
合計70点以上を採用候補、60点台は小額でフォワード検証、50点未満は見送り、のように線引きします。
赤信号・黄信号のサイン集
- 赤信号:損切りなし/理論上無限ナンピン、実運用が未公開、PFがスプレッド悪化に極端に脆弱、入出金で曲線改ざんの痕跡
- 黄信号:成績が単一のブローカーに依存、設定項目が多すぎる、バックテスト期間が短い、実運用の滑りが拡大傾向
- 青信号:実弾・長期・高サンプル、更新履歴が継続、摩擦に対して鈍感なR設計、停止ルールが明記
資金配分とポートフォリオの考え方
- 同時稼働は相関を下げる(手法・時間帯・通貨の分散)。例:ロンドンスキャル+NYブレイク+アジアレンジの組合せ。
- 1EAあたりの口座リスク上限を設定(想定DDの半分程度を口座許容DD上限の目安に)。
- 収益の再投資は段階的に(新高値更新が3回続いたら10%ロット増、DD更新時は自動で減量)。
- 「停止・減量・再開」の基準を事前に文章化し、感情の介入を遮断。
結論:買う前に試算、走らせながら逸脱を検知
EA選びは「見栄えの良い曲線」ではなく、「実績の質」「最悪に備えたリスク」「現実の摩擦に耐えるコスト」の三点を同じ土俵で測ることがすべてです。
PF・DD・RF・R・期待値・停滞期間・総摩擦pipsを数値化し、ブローカーとVPSの環境で再現性を確かめる。
小さく始め、事前に定めた停止・減量ルールで口座を守る。
これらを徹底すれば、宣伝文句から距離を置き、自分の基準でEAを選び抜けます。
数字で選び、数字で運用し、数字で見直す。
この姿勢が、長く生き残るための最短ルートです。
導入と運用はどう始める?MT4/MT5の設定、バックテスト、デモ運用、VPSは必要?
EA導入・運用のはじめ方ガイド:MT4/MT5設定から検証、デモ、VPSまで
EA(エキスパートアドバイザー)を使った自動売買は、感情に左右されずにルール通りの取引を繰り返せるのが強みです。
大切なのは「正しい準備」と「段階的な検証」、そして「運用の基礎体力」を整えること。
本稿では、MT4/MT5の初期設定、バックテスト、デモ運用、VPSの要否判断まで、実務の手順を具体的にまとめます。
環境準備と口座開設の流れ
自動売買は、ブローカー・口座・プラットフォーム・EA・回線の5点セットが揃って初めて回り出します。
焦らず順を追って整備しましょう。
ブローカーと口座タイプの選定ポイント
- 約定力とコスト:スプレッドの狭さだけでなく、約定スピード・スリッページ傾向・取引制限の有無(スキャル不可など)を確認。
- 口座タイプ:手数料別型(ECN/RAW)かスプレッドのみ型(STP/Standard)。スキャルや多頻度EAはECN寄りが有利なことが多い。
- シンボル仕様:追加入力(EURUSD.pro 等)や最小ロット、ストップレベル(最小SL/TP距離)を要確認。EAの条件に合うかが重要。
- ヘッジ/両建て可否:戦略によっては必須。MT5の口座は「ヘッジ型」と「ネッティング型」があるため、EA要件に合わせる。
MT4とMT5の違いと選び方
- MT4:対応EAが豊富。テスターは疑似ティックが基本(外部ティック導入で精度向上可)。
- MT5:マルチスレッドで高速テスト、実ティックや取引所銘柄にも対応。最適化やウォークフォワードが組み込みで扱いやすい。
- EAがどちら用かで選択が決まるのが実情。将来性やバックテスト効率はMT5に分があります。
ダウンロードと初期設定の要点
- 公式/ブローカー配布のインストーラからMT4/MT5をインストール。
- ログイン:口座番号・パスワード・サーバーを入力。接続が安定しているサーバーを選択。
- 時刻同期:Windowsの時刻をNTPで自動同期。時間ズレは指値・ニュースフィルターの誤動作につながります。
- 更新管理:自動アップデートでEAが動かなくなる事例あり。実運用はアップデートの影響を観察し、保守時間を決める。
EAの設置と基本設定
EAは正しい場所に配置し、必要な権限を与えるだけでなく、チャートの前提条件(時間足・シンボル・可視範囲)を揃えることが肝心です。
フォルダ配置と有効化の手順(MT4/MT5)
- MT4:ファイル→データフォルダ→MQL4/Experts にEAファイル(.ex4)を配置。インジケータは MQL4/Indicators。
- MT5:MQL5/Experts にEA(.ex5)。
- プラットフォーム再起動→ナビゲータからEAをチャートにドラッグ&ドロップ。
- チャートの時間足・通貨ペアはEAの仕様に合わせる。マルチタイムフレーム参照EAは必要な時間足のヒストリを事前取得。
自動売買を動かすためのチェック項目
- メインの「自動売買(AutoTrading)」ボタンが緑になっているか。
- EAプロパティの「自動売買を許可」「DLLの使用を許可(必要時)」「WebRequestの許可(ニュース/外部API利用時)」。
- 取引コスト設定:テスター含めスプレッドは「現在値」ではなく固定値で厳しめに設定する方が再現性が高い。
MagicNumberとポジション管理
MagicNumberはEAが自分のポジションを識別するためのIDです。
複数EA/同一銘柄で運用する場合はユニークに設定し、決済やトレールの衝突を防ぎます。
手動決済を絡める場合、コメント欄で区別できる設計だと管理が楽になります。
バックテストの実践
バックテストは「そのEAがどんな相場で、どの程度のリスクで、どう勝ち負けを積み重ねるか」を把握する工程です。
数値だけでなく、エクイティカーブの質まで確認します。
データの品質と取得
- MT4:ヒストリーセンターから1分足データを取得。高精度を求める場合は外部ティック(例:Dukascopy等)を取り込むツールを利用。
- MT5:多くのブローカーで実ティック提供。期間は少なくとも5年以上、戦略が短期なら10年以上が理想。
- シンボル仕様の一致:テストと実運用の小数点桁数、銘柄名サフィックス、スワップ方式、取引時間が一致しているか確認。
テスト条件の設定(スプレッド・遅延)
- スプレッドは通常時より悪化させて検証(例:平均の1.2〜1.5倍)。
- 手数料込みでPips換算。ECN口座はコミッションを必ず入力。
- スリッページ再現:MT5は遅延・スリップのモデリングを設定可。MT4は保守的な固定スリップを上乗せして評価。
- テストモード:短期EAはティック、スイングは1分OHLCでも傾向は掴めるが、エントリーとTP/SLがタイトならティック推奨。
最低限みるべき成績指標と罠
- 最大ドローダウン(%/金額):資金計画の心臓部。カーブが深く長引く期間がどれくらいあるか。
- プロフィットファクター(PF):1.3以上を目安。高すぎる(2.0超)場合は過剰最適化を疑う。
- 勝率と平均損益比(RR):勝率が高くてもRRが悪いと崩れやすい。RR 0.7以上が望ましい。
- トレード数:十分なサンプル(少なくとも数百以上)があるか。
- 期間偏り:特定年だけ好調は警戒。レンジ別(高ボラ・低ボラ、上昇/下降)での安定性を確認。
最適化とウォークフォワードの考え方
- 最適化は「傾向を掴む」ために使いすぎない。パラメータは粗い粒度で。
- ウォークフォワード:過去の一部で最適化→直後の未学習区間で検証。この繰り返しで頑健性を測る。
- モンテカルロ:順序シャッフルやスリッページばらつきで耐性を見る。PFやDDがどの程度劣化しても許容か。
デモ口座でのフォワード運用
フォワードは「いまの約定条件・インフラ」でどう動くかの現実確認。
最低1〜3カ月はデモで回し、日次の挙動を観察します。
小額・段階的な検証プロセス
- デモ(同ブローカー・同口座タイプ)でEAを稼働。バックテストに近い結果か確認。
- 小額のリアル口座で同一設定を複製。デモとの差を把握(スリップ、スプレッド拡大、約定拒否)。
- リスクを0.25〜0.5%/トレード程度で開始し、想定DD内で推移することを確認後に段階増量。
監視と記録のルーティン
- エクイティ曲線、連敗数、平均スリップ、実効コスト(手数料+スプレッド)を週次で記録。
- プラットフォームのJournal/Expertsログにエラーが出ていないか(取引拒否、無効価格、EAエラー)。
- 通知設定:モバイル通知/メールで異常時(ドローダウン閾値・ポジション過多)にアラート。
- 第三者検証:Myfxbook/FXBlueでトラッキング。投資家パスワードを使って閲覧用に公開すると分析が楽。
VPSは必要か?
判断基準と選び方
常時稼働・低遅延が必要なEAはVPSが有利です。
一方、デイトレやスイング中心で日中PCを付けっぱなしにできるなら不要なケースもあります。
必要なスペックと遅延
- 遅延の目安:ブローカーサーバーまで5〜30msが理想(スキャル・高頻度)。100msを超えると約定品質が落ちやすい。
- スペック:2vCPU/3〜4GB RAMでMT4×2〜3/EA数本は十分。複数口座・多EAなら4vCPU/8GB以上。
- ストレージ:SSD必須。ログ肥大化に備え20〜40GBの空き。
- ロケーション:ブローカーのサーバー地域(例:ロンドンLD4、NY)に近いDCを選択。
安定稼働の設定
- Windowsのスリープ/自動再起動を無効。更新は週末メンテ時間に手動適用。
- 時刻同期ツールを導入(NTP)。
- MTの再起動スケジュール:週1回の再起動+ログローテーションで安定度アップ。
- RDP切断時にMTが止まらない設定を確認。UPS/冗長ネットワークがあるVPSだと安心。
実資金へ移行する手順とリスク管理
実運用は「守りが9割」。
ロット設計と停止ルールを先に決め、淡々と運用します。
ロットとリスクの計算
- 1トレードのリスク許容量:資金の0.5〜1.0%を上限の目安に。最大同時ポジションを考慮して総リスクが膨らまないようにする。
- 想定最大DD:バックテストDD×1.5〜2倍を現実的上限とみなし、資金に対する安全域を確保。
- ナンピン/グリッドは「含み損の膨張速度」が速い。ロット逓減や最大段数の制限を必ず導入。
緊急停止・減量のルール
- デイリー/ウィークリー損失が−3%/−6%に到達で自動停止(EA停止スクリプトやアラート活用)。
- 連敗N回(例:7連敗)で半分にロット削減、ドローダウンが回復するまで継続。
- 市場環境変化(極端なボラ拡大、政策イベント)時は一時停止。CPI/FOMCなどは事前にカレンダーで把握。
運用の実務Tips
時間帯・夏時間の影響
ブローカーサーバー時間がGMT+2/+3(夏時間)などで切り替わると、時間指定型EAの動作がずれる場合があります。
EAのタイムゾーン設定がある場合は夏時間切替日に合わせて確認。
アジア時間はスプレッドが広がりやすく、週初・週末や指標前後も拡大します。
スワップやロールオーバー
日付変更(ロールオーバー)時はスプレッド拡大・約定不安定が起きやすく、スワップ3倍デー(多くは水曜)も含めて保有コストが効いてきます。
長期保有EAはスワップ方向を考慮し、テストでもスワップ設定を反映させましょう。
取引コストを抑える工夫
- ECN口座+キャッシュバックの活用。
- ニュース直後の高スリップ帯を避ける時間フィルター。
- 同銘柄に複数EAを重ねる場合、時間帯やロジックが偏らないように分散(逆相関を混ぜる)。
トラブルシューティング
取引が出ない・動かない時
- 自動売買許可、DLL/WebRequest許可、ライセンス期限や認証エラーを確認。
- 必要時間足のヒストリー不足、チャートのスケール制限、銘柄名のサフィックス不一致(例:.m、.pro)。
- 最小距離(StopLevel)が厳しくて注文が拒否されていないか。
- ログに「trade disabled」「invalid stops」「no connection」が出ていないか。
約定が想定と違う時
- スリッページや再クオートが多い時間帯(薄商い、指標直後)を避ける設定に。
- VPSの遅延を計測(Ping)。サーバー地域に合ったVPSへ移転。
- ブローカーの実運用約定品質を比較。口座タイプの変更や別社の検討。
導入チェックリスト(保存版)
- ブローカー/口座タイプはEA要件(ヘッジ、最小距離、コスト)を満たす。
- MT4/MT5のインストール・時刻同期・自動更新の管理が完了。
- EA配置・必要権限(自動売買/DLL/WebRequest)・MagicNumber設定。
- バックテストは十分な期間・保守的なコストで実施、DDとPFを確認。
- フォワードはデモ→小額リアル→段階増量の順に。
- VPSは必要性(常時稼働・低遅延)で判断し、地域・スペック・安定化設定を完了。
- リスクは0.5〜1%/トレードを上限に、停止・減量ルールを事前定義。
- 監視体制(ログ、通知、トラッキング)を整え、週次レビューを実施。
まとめ:小さく始めて、検証と規律で伸ばす
EA運用は「設計どおりに実行される環境」を整えることが成果の出発点です。
MT4/MT5の基本設定を正しく行い、バックテストで戦略の癖とリスクを把握。
デモ・小額リアルでのフォワード検証で現実の約定を織り込んだうえで、VPSや通知・ログの運用体制を固めます。
ロットは常に身の丈、損失を受け入れられるサイズで。
停止・減量のルールを守り、淡々と続けることが、最終的なリターンの安定につながります。
どんなリスク管理と注意点が必要?資金管理、ドローダウン、過剰最適化や詐欺をどう避ける?
EA運用のリスク管理大全:資金管理・ドローダウン対策・過剰最適化と詐欺の見分け方
EA(自動売買)は感情を排してルール通りに取引できる強力なツールですが、「勝てるEA」を探す前に、リスク管理の設計を間違えないことが最重要です。
どんなに優秀な戦略でも、資金管理が甘ければ一度の不運で退場します。
ここでは、実務で使える資金管理とドローダウン対策、過剰最適化(カーブフィッティング)を避ける検証手順、そして詐欺的なEAを見抜くチェックポイントまで、実例とルールで具体的に解説します。
生き残るための基本原則
・損失は「コスト」:スプレッドや手数料と同じく、損失もビジネス上のコスト。
避けるのではなく、受け入れた上で上限を決める。
・一貫性が最優先:その日、その時の気分でロットや設定を変えない。
ルール化し、数値で運用する。
・期待値より先に下振れが来る:利益が積み上がる前にドローダウンが来る可能性を常に織り込む。
資金管理の中核—1トレードの許容リスクを決める
最初に決めるのは「1回のトレードで資金の何%まで失って良いか」。
これがEA運用の土台です。
一般的な目安は0.5~2.0%。
複数EAを同時運用するなら、ポートフォリオ全体で1~3%以内に収めると安全度が上がります。
固定割合リスク法(パーセンテージ法)
・口座残高に対して一定割合の損失額を許容する方法。
・例:口座残高10万円、リスク1%=許容損失1,000円。
ロット計算の実例
ロット=許容損失額 ÷(ストップ幅[pips] × 1pipsの価値)
例:USDJPY、ストップ幅30pips、口座残高10万円、リスク1%(1,000円)。
USDJPYの1ロット(100,000通貨)で1pips≈1,000円、0.1ロットで≈100円。
必要ロット=1,000円 ÷(30pips × 100円)=0.333×0.01ロット=0.033ロット(約3,300通貨)。
ブローカーによりロットとpips価値の定義が異なるため、必ず取引条件で確認。
単利運用と複利運用
・単利:ロット固定。
資金変動の影響が小さく、心理的に安定。
・複利:残高に応じてロットが増減。
長期効率は高いが、ドローダウンも比例して深くなる。
おすすめは「初期は単利→軌道に乗ってから緩やかな複利(四半期ごとにロット見直し)」。
複数EAの資金配分
・相関が高いEA同士(同時間帯、同通貨、同手法)は同時に凹みやすい。
合計リスクを圧縮する。
・基本は等金額配分からスタートし、安定度の高いEAに比重を移す。
・「全EA合計の建玉リスク(合計ストップ損失額)」が口座の2~3%を超えないように設計。
ドローダウンを数字で把握する
ドローダウン(DD)は資産のピークからの最大下落率。
EAの「性格」を表す最重要指標です。
バックテストやフォワードで、最大DDと回復までの期間(リカバリータイム)を必ず確認します。
DDの種類と目安
・最大DD:最悪期の下落幅。
資金計画の前提になる。
・平均DD:通常運転の凹み具合。
日常的な痛みを想定する。
・回復期間:DDから新高値までの時間。
3ヶ月以内が理想、6ヶ月超は要注意。
連敗の可能性をざっくり見積もる
勝率w、取引数Nのとき、起こりうる連敗は想像以上に長くなります。
目安として、N=100、勝率50%でも6~7連敗は十分起こりえる。
勝率40%なら8~10連敗を見ておく。
これを飲み込めるロット設計かを先に決めます。
DD中の運用ルール(減量・停止・再開)
- 減量ルール:直近残高から10%DDでロット半減、15%でさらに半減。
- 停止ルール:20%DD到達、または過去最大DDを更新したら一時停止し、検証に戻る。
- 再開ルール:停止後は最新半年のフォワードでPF>1.2かつDDが想定内に収まることを条件に段階復帰。
レバレッジと証拠金維持率の落とし穴
見かけのレバレッジが低くても、同時保有やナンピンで実効レバレッジが急上昇します。
強制ロスカットは「相場が落ち着く直前」に発動しがちで、最悪の価格で処分されます。
強制ロスカットを避ける安全域
- 証拠金維持率は常に500%以上を目安に(戦略によるが、300%割れは黄色信号)。
- ニュース前後や週明けはスプレッドが拡大。マージン余力を多めに確保。
- ナンピン・グリッド型は「最大段数・最大ロット・強制LC水準」をシミュレーターで前提化。無限に耐える設計は不可。
相関と同時ドローダウン
同じ通貨の同方向ポジションや、同ロジックのEAは凹むタイミングが重なります。
通貨ペア・時間帯・手法を分散し、同時損失の合計が許容範囲に収まるようリスク上限を設定します。
約定とスプレッド悪化に備える実務
ストップ注文の置き方
・論理ストップ(EA内部で監視)ではなく、できる限りブローカー側に実ストップを置く。
・ただし大きなギャップでは滑る前提。
バックテストではスリッページを上乗せ(例:平均0.2~0.5pips、ニュース時は2~5pips想定)。
ボラ拡大/ニュース時の運用
- 高インパクト指標(雇用統計、CPI、政策金利)前後は取引停止、または最大ロットを半減。
- スキャル型は週明け・ロールオーバー(スワップ付与時)・薄商い時間帯を避けるフィルターを。
- スリッページ許容値を設定し、異常悪化時はエントリー拒否にする。
過剰最適化の見抜き方と健全な検証手順
兆候チェックリスト
- 一つの期間だけ極端に成績が良い(直近1年に偏る)。
- パラメータが小数点以下までシビア(例えば期間13.7など非合理)。
- 最大DDが異様に小さく、PFだけ高い(特にグリッド/マーチン隠蔽)。
- 通貨・時間足を変えると急に崩れる(頑健性なし)。
テスト設計(アウトオブサンプル、WF、モンテカルロ)
- データ分割:過去データを学習(最適化)期間と検証期間に分ける。検証期間で利益が残らない戦略は実運用不可。
- ウォークフォワード(WF):複数の学習→検証の連続テストで安定性を確認。
- モンテカルロ:エントリー順序のシャッフルやスリッページをランダム付与し、DDの分布を把握。最悪ケースで耐えられるロットにする。
パラメータの頑健性を確認する
最適値の前後(±20%など)でも成績が大崩れしないかを見る。
山脈のように広い高原(プラトー)がある設定が理想で、尖った一点だけが良い戦略は本番で崩れやすい。
公開成績と販売EAの真偽を見極める
第三者検証とログの重視
- 第三者サイト(例:Myfxbook、FX Blueなど)で「オープン取引・クローズ取引・スリッページ・ブローカー名」が見えること。
- 入出金履歴が開示され、残高曲線の改ざんがないこと。
- 長期のフォワード(最低6~12ヶ月)があるか。デモのみは信用度が低い。
危険なセールストークの特徴
- 「保証」「絶対」「ノーリスク」「1日○%」などの表現。
- グリッド/マーチン系なのに「損切りしないから安全」と強調。
- バックテストの期間が極端に短い、手数料・スプレッド・遅延を未考慮。
- 購入を急がせるカウントダウン、返金保証を過度に強調。
ブローカー選定での詐欺・不正回避
- 約款での約定拒否・ストップレベル・最小距離を確認。スキャル型は約定品質が肝。
- 出金の評判・所要日数・手数料を事前調査。ボーナス条件で出金制限がないか。
- IB(紹介料)目的の誇大宣伝に注意。条件が良すぎる場合は必ず小額で実測する。
運用インフラのリスク対策
VPSと監視
- 約定遅延を下げるため、ブローカーのサーバーに近いVPSを選定。
- 自動再起動・MTの自動再起動設定、通知(メール・プッシュ)を有効化。
- OS更新やメンテ時間を把握し、取引時間外に設定。
冗長化と緊急対応
- 代替回線(モバイル)、予備端末、代替VPSを準備。
- 緊急全決済スクリプト、全EA停止のショートカットを用意。
- 週末クローズ方針(ポジション持越しの可否)をルール化。
毎日の運用ルーティンとKPI
日次・週次で見るべき数字
- 残高・有効証拠金・維持率・含み損益の推移。
- 勝率、平均利益/平均損失、損益比(RR)、プロフィットファクター。
- 最大連敗・最大含み損、保有時間分布、スリッページの実測。
- 月次の損益曲線の歪み(特定の曜日・時間帯に偏っていないか)。
運用ノートの付け方
「何が起きたか」ではなく「次にどう変えるか」を1行で記す。
例:ニュースでスリッページ悪化→重要指標1時間前停止をEA設定に反映。
小さな改善を積み上げることで、同じミスを繰り返さない運用になる。
ケーススタディ:10万円から始める安全運用例
設定例
- 初期資金:100,000円
- EA:トレンドフォロー型1本+レンジ回帰型1本(時間帯分散)
- 1取引リスク:各EA0.5%(合計最大1%)
- 同時保有上限:2ポジション(同方向の相関が強い場合は1に制限)
- ストップ幅:各戦略の想定ボラに合わせ固定(例:30~50pips)
- ニュースフィルター:高インパクト指標前後60分は新規停止
- 停止ルール:-15%で全EA停止、検証に戻る
どのくらいで規模を上げるか
・四半期ベースで、最大DDが想定内かつ月次3勝1敗以上なら、ロットを10~20%だけ増やす(急拡大はしない)。
・残高が20万円に到達後、1取引リスクは0.5%のまま(絶対額は増える)で複利化。
維持率とDDを再点検。
グリッド/ナンピン系EAの特有リスク管理
・本質は「損失の先送り」。
レンジが続けば安定して見えるが、トレンドが継続すると急落。
・最大段数、段間隔、ロット倍率、強制LC水準を先に「数字」で確定。
最悪ケース(高ボラ・スプレッド拡大・ギャップ)で耐えられない設計は使わない。
・週末・指標前はポジション圧縮、証拠金維持率を高く保つ。
中長期の片方向相場に備え、カットルールを用意。
ブラックスワンを想定する
急激なギャップ、異常スプレッド、サーバーダウンはいつでも起こり得ます。
・実ストップの設置+非常時の全決済ボタン。
・VPS監視と二重化。
・高ボラ期間のロット自動縮小ロジック(ATR連動など)を検討。
・週末持越しの上限サイズ。
「起きたらどうするか」を先に決めておくことが、最も効く保険です。
よくある落とし穴と回避策
- 直近の好成績に飛びつく → 最低でも6~12ヶ月のフォワード確認。小額で自分の口座・自分の約定で再現検証。
- DD中にロットを上げて取り返そうとする → 逆に減量。感情はロジックで封じる。
- 複数EAの重ね過ぎ → 相関を測り、合計リスク上限を厳守。
- スワップ・手数料の見落とし → バックテストでコストを上乗せ、実測との乖離を毎月更新。
実装チェックリスト(保存版)
- 1取引リスク(%)とロット計算式を明文化したか。
- 最大DD・停止/減量・再開の数値ルールがあるか。
- ニュース停止や時間帯フィルターを設定したか。
- バックテストはアウトサンプル・WF・モンテカルロまで実施したか。
- 第三者検証の公開成績と自口座フォワードが一致しているか。
- VPSの自動再起動・通知・冗長化・非常ボタンが用意できているか。
最後に:損失をコントロールできれば利益は残る
EAは「優位性の再現装置」に過ぎません。
勝敗を決めるのは、ルール化された資金管理と、数字で定義された停止・再開の判断です。
過剰最適化を避け、詐欺的な宣伝に惑わされず、小さく始めて検証し、合格したものだけに資金を配分する。
損失をコントロールできれば、利益は自然と残ります。
今日から「ロットは式で決める」「止める基準を先に決める」を徹底し、EA運用をビジネスとして設計しましょう。
最後に
EAは定義ルールで自動発注・決済するプログラム。
感情に左右されず24時間高速に取引し、バックテストや複数通貨の分散が可能。
一方、裁量は柔軟だが再現性や速度で劣る。
EAは過剰最適化や想定外、ブローカー品質、運用保守に注意。
MT4/MT5上で動き、損切り・利確・トレイリングなどのリスク管理も自動化。
完全自動や半自動の運用も可能。
まずはデモや少額で検証を。


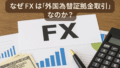
コメント