地震や台風のニュースで「なぜ円が上がるの?」をFX初心者向けに整理します。円が“安全資産”とされる背景、円売りの巻き戻し(キャリートレード解消)、保険金支払い・企業の資金還流による円需要などの仕組みをやさしく解説。加えて、原油高や政策で円高が続かない“例外”の見分け方、初動からエントリー・撤退までの基本手順と注意点も実戦目線でまとめました。
なぜ自然災害が起きると円は「安全資産」として買われやすいの?
自然災害と円高のメカニズム:「安全資産」として買われる理由と実戦対応
大きな地震や台風、水害が発生すると、為替市場ではしばしば円が買われます。
いわゆる「リスクオフ(リスク回避)」局面での円高です。
なぜ、日本で災害が起きたのに日本の通貨が買われるのか。
一見すると直感に反しますが、為替は「資金の出入りの期待」と「ポジションの巻き戻し」で動く世界。
ここでは、円が“安全資産”と見なされる構造的な理由から、過去の事例、例外の見極め方、そして実戦で使えるトレード手順まで、丁寧に解説します。
なぜ円は「安全資産」と呼ばれるのか:5つの土台
1. 日本は世界最大級の対外純資産国
日本は長年、海外に多額の資産を保有してきました。
海外に投資している分、いざという時に「日本勢が外貨建て資産を売って円に戻す(資金の還流)」との期待が生まれます。
実際に全額が即座に戻るわけではなくても、期待だけで先回りの円買いが起こりやすいのです。
2. 経常収支の底堅さが通貨の信認を支える
長期的にみれば、所得収支(海外投資からの利子・配当)を中心とする経常黒字が、円の下支えになってきました。
「継続的に外貨が日本に入ってくる国の通貨は強い」という発想が、リスク回避局面での円買いに拍車をかけます。
3. 低金利ゆえの“調達通貨”=巻き戻しで円高
低金利の円は、海外の高金利通貨を買うための調達通貨として使われやすい(キャリートレード)。
市場が荒れると、投資家はリスクの高いポジションを閉じます。
その際、売っていた円を買い戻す必要があるため、機械的に円高圧力が強まります。
災害は「リスク管理の引き締め」を招きやすく、円買いの着火剤になります。
4. 市場の厚みと流動性、決済インフラの安定性
円は主要通貨のひとつで、市場の流動性や決済インフラが整っています。
パニック時に素早く規模の大きな建玉を動かしたいプロにとって、円は「逃げ道」を提供してくれる通貨です。
結果として、資金の退避先として選ばれやすくなります。
5. 保険金・再保険のフロー期待
大規模災害時には保険金の支払いが急増します。
国内保険会社は外貨建て資産を売って円を手当てする可能性があり、また海外の再保険会社から日本へ支払いが入るケースもあります。
これらの「円需要が増える」という期待が、ニュース直後の円買いを誘発します(実際のキャッシュフローは後日であっても、先回りの思惑で動く)。
“自然災害=円高”の実態:短期と中期で分けて考える
短期(ニュース直後~数日):ポジションの巻き戻しが主役
市場が最初に反応するのは「ショック」と「不確実性」です。
キャリートレードの解消、リスク資産からの退避、保険金需要の先回り買いなどが一斉に出やすく、円クロス(ドル円、ユーロ円、豪ドル円など)で円高方向にギャップが開くこともあります。
薄商い時間帯(早朝・週明け)にニュースが重なると、スプレッド拡大とともに荒い値動きが出やすい点にも注意が必要です。
中期(数週間~数カ月):需給と政策、貿易構造が効いてくる
インフラ被害で輸入燃料が増える、サプライチェーン寸断で輸出が減る、といった実体経済の影響がボディーブローのように効いてきます。
災害対応で金融緩和期待が強まれば、円安に振れやすくなる局面もあります。
2011年の東日本大震災では、直後は円高が加速したものの、その後は介入や政策対応、エネルギー構造の変化が中期のトレンドに影響しました。
「短期は巻き戻しで円高、時間が経つとファンダメンタルズで方向感が変化し得る」という二段構えで考えることが重要です。
過去の主な事例から学ぶポイント
1995年 阪神・淡路大震災
大規模災害を受け、円は対ドルで過去最高値圏まで買われました。
対外資産の還流期待とキャリートレード解消が背景。
流動性が低い時間帯の急伸や、当局のけん制(口先介入)など、ボラティリティ管理の重要性が改めて意識された局面です。
2011年 東日本大震災
発生直後に円高が急伸し、史上最高値を更新。
その後、G7協調の円売り介入が実施され、急速に反転する展開となりました。
「極端な円高は当局の介入リスクが高い」ことを市場参加者に再認識させた象徴的なケースです。
2016年 熊本地震 ほか
円高反応は見られる一方で、規模やタイミング、並行するグローバル要因(米金利、株式市場の動揺)によって値幅はまちまち。
単体の災害ニュースだけでなく、同時期の世界的なリスクイベントの有無が値動きの大きさを左右します。
よくある誤解と「例外」の見極め
誤解1:「保険金の支払い=必ず円買い」
実際の資金の出入りは複層的です。
再保険で海外から円が流入する面もあれば、保険会社が外貨を現地で現金化して円転を分散する場合もあります。
市場は“期待”で先に動きやすいものの、日次で単純なフローに帰着するわけではありません。
誤解2:「国内災害なら常に円高」
被災の範囲が広く、景気下押しや電力供給不安が強ければ、金融緩和観測が先走り円安に振れることもあります。
逆に海外で大災害が起き、世界のリスク資産が売られる場合でも、キャリー巻き戻しで円高になりやすい。
場所よりも「市場全体のリスク許容度」を優先して把握しましょう。
誤解3:「円はいつでも最強の安全資産」
円の“安全資産”性は相対的です。
米ドルやスイスフランもリスクオフで買われます。
日本の金利政策が極端に緩い局面では、対ドルでの円高が伸びづらく、代わりに“円クロス”全般での円買いが目立つこともあります。
例外のサイン
- 金融当局の口先介入・実弾介入の可能性が高い(異常な速度の円高)
- 同時にグローバルなドル資金需給が逼迫(ドル高・円高が相殺されやすい)
- 災害後の政策期待(緩和・補正予算)で金利差拡大観測が優勢
- エネルギー価格高騰で貿易赤字拡大が意識される
実戦の視点:ニュースからエントリーまでの手順
1. 初動の整理(5~30分)
- 対円クロスの広範な下落(円高)か、ドルストレートの動きかを確認
- 株式先物(日本・米)、VIX、米金利、商品市況の同時反応を見る
- 主要ニュース(当局発言、被害推計、原発・電力供給関連)をチェック
2. エントリーの考え方
- モメンタム狙い:ブレイク後に出来高を伴って走るなら順張りで短期回転
- スパイク・リバーサル狙い:極端なワンウェイ後、当局けん制や要人発言で反転の兆しが出たら逆張りを検討(介入リスクは特に留意)
- 通貨選別:ドル円だけでなく、対豪ドル・対新興国通貨など「キャリーの解消」が出やすいペアを優先
3. 損切り・利確ルール(例)
- 急変時は通常の半分以下のポジションサイズに抑える
- ボラティリティに応じたストップ(ATRの1~1.5倍)と時間軸別の利確ポイントを事前に設定
- 窓開けスタート時は、窓の半分戻し・全戻しを節目として分割決済
どの指標・フローをチェックするか
- 当局の発言(財務省・日銀):異常な円高速度にはけん制が入りやすい
- MOFの対外証券投資(週次)や四半期の国際収支:実フローの手掛かり
- 保険・再保険会社の決算・開示:大口の為替ヘッジや外債売却の示唆
- エネルギー価格(原油・LNG関連):中期の貿易収支と円の需給に影響
- 米金利・米株・VIX:グローバルなリスク許容度の温度計
通貨ペア別の着眼点
ドル円(USD/JPY)
世界的なドル需給と円のキャリー巻き戻しが綱引きに。
米金利が急低下し株が崩れる典型的なリスクオフでは円高が走りやすい一方、ドル資金が逼迫するストレス局面では相殺されやすい。
口先介入の影響を最も受けやすいペアでもあります。
豪ドル円・NZドル円(AUD/JPY, NZD/JPY)
キャリーの縮小が直撃しやすく、リスクオフ時は下落が大きくなりがち。
テクニカルの節目(200日線や直近安値)を割れると加速しやすいので、モメンタム狙いと相性が良い場面が多いです。
ユーロ円(EUR/JPY)
欧州のニュースフロー(金融安定や地政学)と重なると値動きが拡大。
ECBの政策期待と絡めて、トレンドの持続性を見極めましょう。
テクニカルと組み合わせるコツ
- ニュース直後は短期足(1~5分)でギャップと出来高の確認、落ち着いたら15分・1時間足で戻り売り/押し目買いの候補を設定
- ボラ急拡大時は移動平均よりも価格帯出来高・VWAP・直近スイングの高安が効きやすい
- イベントドリブンでは「第一波(ニュース)→第二波(当局発言・データ)→第三波(実フロー観測)」の波形を意識
リスク管理:生き残るための3原則
- スプレッド拡大と約定滑りを織り込む(成行を多用しない、指値は余裕を持つ)
- ポジション分割と時間分散(同方向に一括で大きく建てない)
- 介入・要人ヘッドラインの警戒(アラート設定、発言時間帯の建玉圧縮)
まとめ:構造を知り、波に飲まれず乗る
自然災害で円が買われる背景には、対外純資産の厚み、キャリーの巻き戻し、保険・再保険の円需要期待、そして主要通貨としての流動性といった複数の土台があります。
初動は“期待とポジション解消”で円高に振れやすく、その後は政策や貿易構造などファンダメンタルズがトレンドを形作ります。
例外も多いため、当局のスタンス、グローバルなリスク許容度、エネルギー価格といった周辺環境のチェックが欠かせません。
ニュースに飛びつくのではなく、「何が買われ、何が売られているのか」「今の円高は巻き戻しなのか、実需へシフトしているのか」を切り分け、適切なサイズとストップで臨むこと。
これが、混乱の相場で生き残り、機会をものにする最短距離です。
保険金支払い・企業の資金還流(レパトリエーション)はどう円高を招くの?
保険金フローが為替に与える仕組みをゼロから分解
自然災害のニュースで円が急騰する場面は珍しくありません。
その背景のひとつが「保険金支払い」と「企業のレパトリエーション(資金還流)」です。
いずれも“円を調達する実需”を生み、短期的には需給バランスの偏りが為替を動かします。
ここでは、どのような資金の流れが実際に円買いを生むのか、段階を追ってシンプルに整理します。
国内損保の資金調達プロセス
大規模な災害が発生すると、国内の損害保険会社(火災・地震・自動車など)は多額の保険金を円で支払います。
支払い原資は主に以下の順番で手当てされます。
- 手元流動性(現預金・短期運用資産)の取り崩し
- 国内資産(JGBや国内社債・株)の売却やレポ調達
- 海外資産の売却や為替ヘッジの解消(ここが円買いに直結)
- 再保険からの回収金(多くは外貨で受領→円転)
保険会社は資産の一定割合を海外に分散投資しています。
保険金支払い規模が手元流動性を超えると、米国債や海外社債・株式の売却、あるいは保有外貨資産のヘッジ解消(外貨売り・円買い)が必要になります。
外貨建て資産の売却やヘッジ解消=市場で円を買い戻す行為なので、円高圧力になります。
再保険の逆流(海外→日本)と円買い
大口の自然災害では、損害の相当部分を海外の再保険会社が負担します。
スイスやドイツ、ロイズ(英国)、バミューダなどに本社を置く再保険会社から日本の損保へ外貨で資金が戻るのが通例です。
- 海外再保険会社がUSD/EURで支払い→日本側が受領
- 日本側は受け取った外貨を円に転換して保険金支払い原資へ(もしくは外貨で受けて既に払った分を穴埋め)
- この外貨売り・円買いのフローが断続的に発生
注意点は、タイムラグがあること。
保険金支払いの初動は国内損保の手元資金とヘッジ解消で賄われやすく、再保険からの回収は数週間~数カ月かかることが珍しくありません。
したがって、マーケットでは「まず期待で円が買われ、後から実需が追随」しやすい構図になります。
ヘッジ解消・調達通貨の巻き戻し
多くの機関投資家は、外貨建て債券に対して通貨ヘッジ(先物・フォワード)をかけています。
保険金支払いのために外貨建て資産を圧縮すると、対応するヘッジも不要になるためヘッジの買い戻し=円買いが発生します。
さらに、円は長年「低金利の調達通貨」でもあるため、グローバル投資家のキャリートレードが災害時に巻き戻され、円ショート解消の買い戻しが重なりやすいのも特徴です。
企業のレパトリが円高を誘発するロジック
災害後は企業も設備復旧や在庫補充、サプライチェーン再構築のために資金需要が増えます。
ここで起こるのが海外に滞留していた現金・預金、外貨建て運用資産の円への還流です。
復旧・復興に必要な支出と資金源
- 国内工場・オフィスの復旧、臨時の前払い、労務費の増加などで円建て支出が急増
- 資金源として、国内借入の増額、社債発行、海外子会社からの配当・余剰資金の吸い上げ、外貨資産の売却が選択肢
- 海外からの送金や外貨から円への転換が増えれば、外貨売り・円買いのフローが出る
特に日本は対外純資産が大きいため、平時に海外へ滞留している現金が多い企業ほど、必要時にレパトリを選びやすく、これが円需要になります。
期末・配当・税支払いと重なるタイミング
3月期決算が多い日本では、期末や配当・税納付期にレパトリが増えやすい季節性があります。
災害がこのタイミングと重なると、もともとの円需要に上乗せが起き、相場のモメンタムを強めやすいのが実務上の注意点です。
輸出企業と輸入企業の相殺関係
輸出企業は外貨売り・円買い(受取外貨を円転)主体、輸入企業は外貨買い・円売り主体です。
災害直後は生産停止で輸入需要(原材料・エネルギー)が一時的に減る一方、復旧局面では資材・エネルギーの輸入増加で中期的に外貨需要が膨らみやすい。
つまり、初期は円高、後期は円安圧力といった“二段構え”になりがちです。
タイムラインで見る「初動→第二波→反動」
ニュース直後の数時間
- 「安全資産」意識と円ショートの巻き戻しが先行し、テクニカルのストップも誘発
- ディーラーは保険金支払い・レパトリ期待を先回りし、短期的に円買いが優勢に
数日~数週間
- 損保のヘッジ解消や一部の外貨資産売却、企業の初期レパトリで実需の円買いが断続的に出る
- 海外再保険からの回収は契約・査定プロセス次第で遅行しがちだが、マーケットは“受け取り見込み”を前倒しで織り込む
反動局面(輸入増・政策対応)
- 復旧が進むと資材・エネルギー輸入が増加し、外貨需要が上振れして円安圧力が台頭
- 財政出動・装置更新で景気押し上げ→金利観測・金融政策期待が為替へ波及
- 当局(財務省・日銀)のコメントやオペがボラティリティを抑制することも
実務で使う観測ポイントとデータ源
損保・再保険関連の手掛かり
- 大手損保(東京海上HD、MS&AD、SOMPO)の開示資料:災害による支払見込み、再保険回収見込み、通貨ヘッジ比率
- 日本損害保険協会の発表:支払件数・見込み額
- 海外再保険(スイス再保険、ミュンヘン再保険、ロイズ等)の「災害ロス推定」アップデート
- 決算期・月次運用レポート:外貨建て資産とヘッジの増減
フローを示す公的統計と市場指標
- 財務省「対外・対内証券売買動向(週間)」:日本投資家の外債・外株の売買(外債売りが増えると円買い圧力の示唆)
- 国際収支統計(経常収支・第一次所得収支):海外からの所得環流の増減
- 為替スワップ・クロスカレンシー・ベーシスの動き:短期の外貨調達・円調達の逼迫感
- オプション市場(リスクリバーサル、インプライドボラティリティ):円コール需要の膨らみ
トレード戦略に落とすときの考え方
ニュースと実需フローのズレ、二段階の波、そして反動を前提にシナリオを用意します。
シナリオ別のエントリー例
- 初動のショートカバー主導:主要サポートの上抜け・下抜けで短期フォロー。目標は直近ピボットや1日のATR程度。長居しない。
- 実需の第二波狙い:数日置いてから、損保開示やモニターで外債売りが観測されたら押し目買いで参加。再保険回収のニュースヘッドラインが出る前に仕込むのが理想。
- 反動(輸入増・復旧輸入):資材輸入見込み・火力発電稼働増などで外貨需要が顕在化したら、円高分の巻き戻しに備える。テクニカルでは日足の転換サインを優先。
ポジション管理と撤退基準
- イベント相場のボラ上振れに備え、想定ボラ×時間で損切り距離を決定(例:日中ATRの0.8~1.2倍)
- ニュースの「後追い」は禁止。初動から30~60分の遅れ参戦は、必ずテクニカルな再エントリー条件を待つ
- 複数ポジションで段階利確。再保険回収の確度が高まる局面では一部をスイングへ
ありがちな勘違いと回避法
ケースA:国内災害でも円安が進む場合
- 災害規模が小さく、保険金支払いが手元流動性で十分→外貨売り・円買い不要
- エネルギー・資材輸入が直後から増加→外貨需要が増え、円安に傾く
- 海外金利急騰・日米金利差拡大が同時進行→ファンダが円安を上書き
ケースB:保険が海外に付保されている比率が高いとき
- 海外再保険が大半を負担→日本側の資産売却やヘッジ解消が限定的
- 回収が外貨のまま積み上がり、円転タイミングが分散→為替への一時的な影響は薄まる
- 一部の損害が海外拠点(例:海外工場)に及ぶと、現地通貨での支払い・調達が増え、円需要は相殺される
コンパクトなチェックリスト
- 被害規模のオーダー:保険金支払見込みが1兆円級か、再保険回収見込みの有無
- 損保のヘッジ比率:外債ヘッジの巻き戻しがどれくらい出る設計か
- タイミング:期末・配当・税納付期との重なり、再保険支払いサイクル
- 貿易の反動:復旧に伴う輸入増の見通し(エネルギー・資材)
- データ:財務省の週次フロー、保険会社の開示、損保協会、ベーシス・オプションの歪み
結び:フローの全体像を押さえて冷静に行動
自然災害で円高になりやすい本質は、円で支払うための現金需要(損保の支払い・企業の資金還流)と、外貨ポジションやヘッジの解消が重なるためです。
初動は期待とポジション調整、次いで実需の第二波、最後に輸入増などの反動という流れを前提に、ニュースを鵜呑みにせずフローの出所・規模・タイミングを分解して判断しましょう。
データで裏取りし、値動きが落ち着くのを待ってから戦術を当てはめることが、結果的に最も効率の良い立ち回りになります。
いつも円高になるとは限らない?例外ケースと見極めポイントは?
自然災害と円相場:なぜ上がる時があるのか、上がらない時は何が違うのかを実務目線で整理
自然災害のニュースの直後に円が買われることは珍しくありません。
一方で、まったく円高にならない、むしろ円安が進むこともあります。
ここでは、災害と円相場の関係を「資金フロー」「ポジション」「政策・商品市況」の3本柱で分解し、例外パターンまで見分けられるように解説します。
円買いが発生しやすいときの流れ(フローの連鎖)
まず、円高が起きやすい典型的なプロセスを、短時間でイメージできるように並べます。
- リスク回避の初動:災害ヘッドライン直後は短期勢のポジション縮小(円売りの解消)で円が上がりやすい。
- キャリーの巻き戻し:円は低金利で借りやすい通貨。高金利通貨買い・円売りの持ち高が多い局面では、一斉に外貨ロングが解消→円買い。
- レパトリ(資金還流)思惑:保険金の支払い、復旧資金需要、国内企業の倉庫・工場復旧などで「円を国内で使う」期待が先回りで価格に織り込まれる。
- オプションヘッジの偏り:短期ディーラーが円コール(USD/JPYのプット)需要を高め、下方向のガンマが効きやすくなる。
重要なのは、この「円高の連鎖」はニュースの瞬間から数時間~数日の短い時間に集中しやすいこと。
根拠は、最初に動くのは常に「既存ポジションの解消」だからです。
根っこの実需(輸出入や保険金の最終フロー)が為替に乗ってくるのはもっと先の話になりがちです。
円高にならない、または円安が進む力学
次に、同じ「自然災害」でも円が強くならない条件を整理します。
ここを押さえると、見た目が似ているニュースでも値動きの差を説明できます。
- エネルギー・資材の輸入増観測:電力需要の逼迫や火力代替で、原油・LNG・石炭の輸入額が膨らむ見通しになると、貿易赤字拡大が意識され円安要因に。
- 金融政策の方向:景気下押し=追加緩和観測が強まると、金利差拡大(米国>日本)で円安圧力。量的緩和や長期金利の抑制観測も同様。
- 地理と規模の問題:被害がサプライチェーンを広範囲に直撃し、主要輸出の停止長期化が見込まれる場合、外貨の稼ぎが細る観測→円安方向。
- グローバルの「主役」が米ドル:世界同時にリスクオフが強いと、まずは米国債買い・米ドル需要が優位になりやすい。米ドル高・円高の綱引きで、対ドルでは動かない(または円安)。
- 相場の事前ポジション:すでに極端な円ロングが溜まっていると、悪材料でも利確の円売りが先行し逆走しやすい。
- 政策・介入の蓋:円が行き過ぎれば当局の口先や協調行動が意識され、ショートカバーの円売りが出ることも。
ニュース直後に使える「見極めの順番」
短時間で方向性の確度を高めるためのチェック手順です。
上から順に見ていき、合致数が多い方向を優先します。
- 価格の初動と板の厚み
- 最初の5~15分でUSD/JPYが大きく下に走るか(円高)、上髭を何度も叩かれるか。
- 東京時間なら仲値前後の買い需要に吸収されるかどうかも確認。
- 株式・金利の同時確認
- 日経先物が急落、JGB先物が買われる(利回り低下)ならリスク回避色が濃い=円高に同調しやすい。
- 逆に米金利上昇と米株先物堅調なら、対ドルでは円が上がりにくい。
- 商品市況の反応
- 原油・LNG指標上昇なら輸入負担増の思惑→円安圧力。金価格急伸はリスクオフ色を補強。
- オプション市場の歪み
- USD/JPYの25デルタ・リスクリバーサルがマイナス方向に拡大=円コール需要増で円高シグナル。
- 政策ヘッドライン
- 財政出動・補正予算・追加緩和の観測が同時に出ると円安方向にブレやすい。
- 被害の質
- 発電・港湾・物流の停止が長期化する見込みか。復旧が早いと見れば「巻き戻し限定」に留まりがち。
災害のタイプ別に見た通貨インパクトの癖
- 地震・津波:初動の「円買いの巻き戻し」が走りやすい。規模が極端に大きい場合、日数が経つとエネルギー輸入増観測で円安へ反転することも。
- 台風・豪雨:季節性があり、輸送・小売の一時的停滞が中心。初動の反応は比較的短命になりやすい。
- 電力関連トラブル:供給制約→工場停止→輸出減の見通しが立つと円安圧力が台頭しやすい。
- 海外での大規模災害:リスクオフの中で円が広範に買われる一方、対ドルで伸び悩むことがある。
短期~数日の取引設計(時間軸での考え方)
- フェーズ1(0~30分):ポジションの解消波
- ニュース一報でスプレッドが広がる。成行は避け、5~15分の最初の押し戻りを待つ。
- テクニカルは1~5分足の直近高値・安値ブレイクのみを採用。薄い板ではダマシも多いのでサイズは軽く。
- フェーズ2(30分~半日):見出しの二次波
- 被害推計、政府見解、稼働停止ニュースなどが追加される時間帯。初動の方向と整合するかを都度確認。
- VWAP回帰や前日安値・高値がレジサポとして機能しやすい。
- フェーズ3(翌日~):実需と政策の現実化
- エネルギー価格・金利・株式が噛み合ってくる。ここで方向が逆転することもあるため、持ち越しは慎重に。
「例外」になりやすい条件のチェックリスト
- 世界同時リスクイベントが重なっている(米雇用統計、FOMC、欧州銀行不安など)。
- 直前まで円高トレンドが強く、CFTCなどで円ロングが積み上がっている。
- 政府・中銀が速やかに緩和的なメッセージを出した。
- 発電・港湾・基幹道路の被害が深刻で、復旧に時間がかかる見通し。
- 原油やガスの先物が同時急騰。
- 協調的な市場安定化策(為替への言及、スワップラインなど)が観測される。
通貨ごとの「組み合わせ」で見た動き方の目安
- 対ドルの組み合わせ:米金利が低下(債券買い)なら円高になりやすいが、米ドル自体が安全資産として最強に買われる局面では伸び悩む。
- 対資源通貨の組み合わせ:原油・銅・鉄鉱石が軟化なら資源国通貨が売られ、円高が進みやすい。資源高ならその逆。
- 対欧州通貨の組み合わせ:欧州の金融不安や地政学でユーロ売り・円買いが連鎖しやすい。
実務で使える「早見表」的な判断フレーズ
- 初動でUSD/JPYが下へ、日経先物は-2%、米10年金利は低下、原油は横ばい→円高継続の公算。
- USD/JPYは下げ渋り、米金利は上昇、原油は急騰→円高は続きにくい、反発警戒。
- オプション市場で円コールのボラ急騰、スポットは前日安値を難なく突破→ショート継続寄り。
- 要人発言で緩和・財政の連呼、株が下げ止まる→利食いを優先、様子見へ。
エントリーと撤退の具体例(あくまで一案)
- 下方向ブレイクの追随
- トリガー:5分足で直近安値を終値で明確に割れ、出来高(ティック)が増加。
- 損切り:直近戻り高値の上に数pips。
- 利確:前日の安値、もしくはATR1.0分の値幅達成で半分、残りはトレール。
- 戻り売り
- トリガー:VWAPまたは20EMAへの戻りで上髭が連発し、レジスタンスを背にショート。
- 損切り:レジスタンスを1本足でクローズ超え。
- 例外サインが出た時の反転
- トリガー:原油上昇+米金利上昇+当局の緩和示唆が同時に出現、5分足で安値切り上げ。
- 方針:ショートは手仕舞い。むやみにロング反転はしない(ボラが高い)。
失敗を減らす行動原則
- ニュース単発で飛びつかない:最低2つの別ソース、2つの市場(為替以外)で裏取り。
- サイズは段階的に:初動は小、二次情報で追加、逆行で早めに間引く。
- 時間帯に気を配る:東京仲値、ロンドンOPカット、NYオープンはダマシが増える。
- ギャップは半分しか追わない:大窓の後は半値戻し・半値押しを起点に計画。
- 政策の一声で世界は変わる:口先介入や協調行動の兆しが出たら方針を一旦白紙に。
ケーススタディ的な思考訓練
- 条件A:国内で大規模地震、株急落、米金利低下、原油横ばい、追加緩和言及なし
- 解釈:円高優勢。初動の戻り売りを狙う。
- 条件B:電力供給が長期停止、原油急騰、政府が補正と緩和の同時示唆
- 解釈:初動の円高は短命。利確優先、反発の円安シナリオも準備。
- 条件C:海外での巨大災害、VIX急騰、米国債急騰、米ドルも買われる
- 解釈:円は広範には強いが対ドルは伸びにくい。対資源通貨での円買いが有利。
把握しておきたいデータと速報の入口
- 市況系(株・債券・コモディティ)の同時監視:米金利、原油、金、日経先物。
- オプションの歪み:25Dリスクリバーサル、インプライド・ボラの面(期限別)。
- 政策シグナル:政府・中銀の会見予定、声明、記者発表。
- 保険・再保険関連の初期推計:支払見込みは日単位で変わるため、絶対視しない。
まとめ:法則は「条件付き」。初動の巻き戻しと中期の実需を分けて考える
自然災害で円が買われるのは、「安全資産」や「キャリー解消」といった短期の需給が一気に動くからです。
しかし、それが持続するかどうかは、エネルギー輸入、政策対応、被害の質と復旧速度、そして世界のリスク選好という条件で簡単にひっくり返ります。
実務上は、初動の円高を追うかは「別市場の同意(株・金利・商品)」と「オプションの歪み」で確認し、例外シグナル(原油高+緩和観測など)が点灯したら利食いと撤退を優先する。
この切り替えの速さが成否を分けます。
法則に頼り過ぎず、条件を数えて意思決定する姿勢を保ちましょう。
最後に
災害時はリスク回避で円が買われやすい。
日本は対外純資産が大きく経常黒字、円は低金利の調達通貨で巻き戻しが起き、流動性と保険金需要期待も円買い要因。
短期は円高が出やすいが、中期は輸出減・輸入増や政策で方向が変わる。
初心者は薄商いの変動とスプレッド拡大に注意。
ニュース直後はポジション解消が主因、様子見や指値の活用で無用な追随を避けよう。
政策・介入ヘッドラインも注視。
損切り幅は広めに。
レバは控えめ。
落ち着いて。
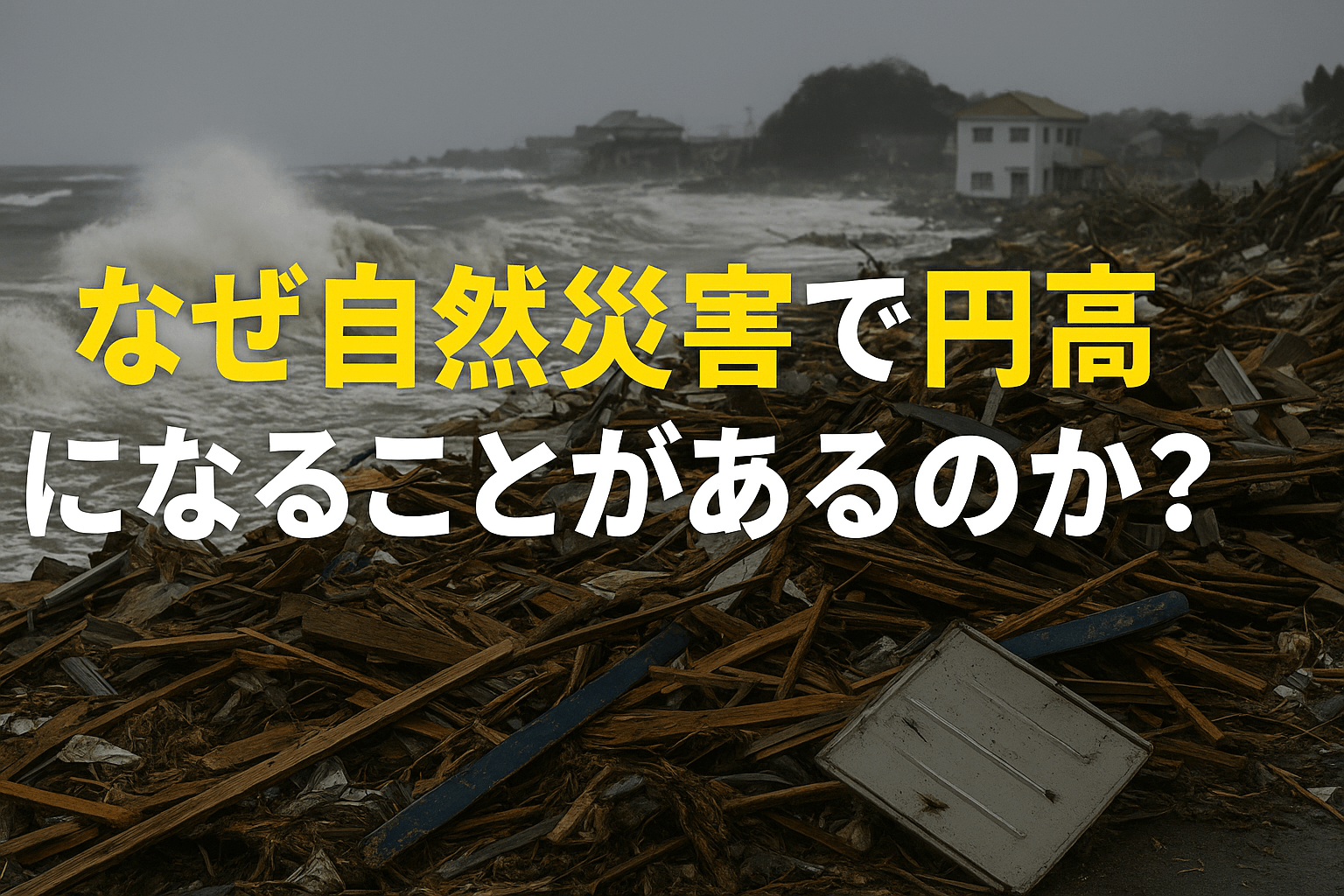
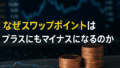
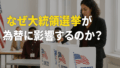
コメント