残高とクレジットの違いが曖昧だと、MT4/MT5での証拠金計算やロット設計は一瞬で破綻します。本稿は、ブローカー別の計上ルール(Equity/Free Margin/維持率への反映)、付与・剥奪・出金時の挙動、含み損・ヘッジ・ロスカットへの影響を体系化。さらに残高×クレジット比率ごとのリスク%とロット算出テンプレ、実機検証チェックリストまで提供。クレジットを“攻め”でなく“盾”として使うための実務ガイドです。
「残高」と「クレジット」は何が違い、MT4/MT5や各ブローカーではどちらが証拠金・ロット計算に反映されるのか?
「残高」と「クレジット」の根本的な違い
残高は、確定損益まで反映された「自分の資金」です。
入出金、スワップ・手数料の確定、決済済み損益だけが影響します。
一方、クレジットはブローカーが付与するボーナスやプロモーションの性質を持つ「条件付きの資金」で、原則として出金できません。
多くのブローカーでは、クレジットは口座の補助資本として扱われ、証拠金余力を押し上げたり、ドローダウンのクッションになったりしますが、付与条件・剥奪条件が設定されている点が本質的な違いです。
MT4/MT5での表示と計算の基本
MT4/MT5の「取引」タブには、以下の指標が表示されます。
- Balance(残高)…確定済みの口座資金
- Equity(有効証拠金)…残高+評価損益(±)+クレジット(ブローカー仕様で計上される場合)
- Margin(必要証拠金)…保有ポジションに必要な拘束額
- Free Margin(余剰証拠金)…Equity − Margin
- Margin Level(証拠金維持率)…Equity ÷ Margin × 100%
- Credit(クレジット)…付与ボーナス。表示の有無や計上方法はブローカー設定による
重要なのは「Equity」と「Free Margin」と「Margin Level」の算出にクレジットが入るかどうかがブローカーによって異なる点です。
MT4/MT5のプラットフォーム自体は「計上可能なフィールド」を持ちますが、最終的な反映ルールは各社のサーバープラグイン設定(ボーナス・クレジットモジュール)に依存します。
クレジットが証拠金・ロット計算に反映される代表的なパターン
パターンA:フル計上(最も一般的)
特徴:クレジットがEquityに加算され、Free MarginとMargin Levelにも反映。
効果:クレジット分だけ新規ポジションの発注可能ロットが増え、ドローダウン耐性も向上。
注意:出金や一定の評価損(例えば「Equity ≦ 残高」や「Equity ≦ 残高−X%」等の条件)でクレジットが即時剥奪される場合があります。
剥奪が起きるとEquityが瞬間的に減少し、維持率が急落→即ストップアウトにつながるリスクがあります。
パターンB:マージン補助のみ(ドローダウンクッションなし)
特徴:新規建玉の必要証拠金計算には反映されるが、浮動損によるEquityの下支えには使えない(損失の穴埋めには充当されない)。
効果:建玉可能ロットは増えるが、含み損が拡大すると維持率低下は「クレジットが無い場合とほぼ同等」。
注意:単に最大ロットが増えるだけで、損失耐性が上がったと誤認しやすい。
損失局面では脆弱。
パターンC:クレジットをEquityに計上しない(例外的)
特徴:取引タブにCreditが表示されても、Equity・Free Marginに反映しない。
効果:実務上は「残高ベースの口座」とほぼ同じ。
ボーナスはプロモーションの指標に過ぎず、発注能力に影響しない。
注意:まれですが存在します。
ブローカー規約を必ず確認してください。
実際の計算例(フル計上型を想定)
条件:レバレッジ1:500、EURUSD、契約サイズ100,000、口座通貨USD、EURUSD=1.1000。
- 残高1,000USD、クレジット1,000USD、未決済損益0の時
Equity=2,000、Free Margin=2,000、Margin Level=∞(未保有) - 1.0ロットを新規買い(必要証拠金の近似)
必要証拠金=(100,000 EUR ÷ 500)× 1.1000 ≒ 220 USD
保有後のFree Margin=2,000 − 220 = 1,780 - 含み損が−1,600に拡大すると
Equity=2,000 − 1,600 = 400、Margin=220、Free Margin=180、維持率=400 ÷ 220 ×100 ≒ 181.8%
同条件でクレジットが計上されない場合、初期Equityは1,000となり、同じ1.0ロットの含み損−1,600に達する前にストップアウト水準に接近します。
つまり、クレジットがフル計上なら「建てられる・耐えられる」一方、剥奪や非計上なら一気に脆弱になることが理解できます。
ロット計算にどちらを使うべきか
理論上、MT4/MT5は新規発注時に「Free Marginが必要証拠金以上あるか」を判定するため、クレジットがEquityに入る仕様ならロット上限は押し上がります。
しかし実務では、以下の優先順位を推奨します。
- リスク管理の基準…「残高」ベースを原則(特にクレジット剥奪条件が厳しいブローカー)。
- 発注可能ロットの上限…「現在のEquity(クレジット込み)」を参考にしつつも、安全係数をかける。
- 損切り幅からの逆算…pipsあたりの価値(ティックバリュー)×ロット×損切りpips ≤ 許容損失(残高のX%)で設計。
クレジットを前提にロットを増やすと、出金やルール違反でクレジットが消えた瞬間に維持率が急落するため、EA/裁量とも過大ロット化のリスクが高まります。
特に「Equityがクレジット閾値を割り込んだら即剥奪」のルールは危険度が高いです。
ブローカーごとの相違点と確認ポイント
クレジットの取り扱いは約款とサーバー設定次第です。
以下を必ず確認しましょう。
- クレジットがEquity/Free Margin/維持率に計上されるか(テクニカル仕様)。
- 剥奪条件…出金時、内部振替、一定のドローダウン到達、ヘッジ・スキャル規制などの約款違反。
- ストップアウト水準…維持率が何%で強制ロスカットか(例:20%/50%など)。
- ボーナスの期限…有効期限、ロールオーバー条件、ロット消化条件(取引量要件)。
- レバレッジ段階制…残高やエクイティに応じて最大レバレッジが逓減するか。クレジットを含む/含まないの解釈。
- プロモーション種別…入金ボーナス(クレジット型/残高付与型)、口座ごとの差(スタンダード/ECN等)。
「残高付与ボーナス」と「クレジット型ボーナス」の違い
一部のブローカーはボーナスを残高に直接計上します。
この場合は「出金可能(条件付き)」なケースも多く、計算上も純資産そのものが増えるため、クレジット剥奪型に比べてロット設計が安定します。
対してクレジット型は、増えるのはあくまで取引能力であり、ボーナス自体は出金不可が一般的。
利益の出金に条件が付くこともあります。
リスク管理の実務:5つの原則
- 剥奪を前提にする…ロット設計は残高ベース、クレジットは「ゼロ化しても安全」な範囲に限定。
- 最大許容損失=残高の一定%…1回のトレードで1〜2%を基本線に、連敗時は逓減。
- 含み損管理はEquityで監視…評価損が増えたらロット縮小、分割決済やヘッジで維持率を守る。
- 出金前に建玉軽量化…出金でクレジットが剥奪されるタイプは、必ずポジション縮小→維持率再計算→出金実行の順。
- ストップアウト閾値にマージンを…維持率閾値+20〜30%の安全域を常に確保。
検証方法:自分の口座でどう計上されているか
- ステップ1:ポジション未保有で「残高・クレジット・Equity」をメモ。
- ステップ2:最小ロットで新規発注、必要証拠金とFree Marginの減り方を確認。
- ステップ3:同一ロットで数ポジ追加し、維持率の推移を見る。クレジットがEquityに入っていれば、明確に耐性が上がるはず。
- ステップ4:サポートに「クレジット剥奪条件」「出金時の取扱い」「レバレッジ段階制への反映」を明文化してもらう。
よくある落とし穴
- 出金→ボーナス剥奪→維持率急落→即ロスカット。出金は建玉縮小後に。
- 消化ロット要件の未達成で利益出金不可。条件達成前の大ロットはむしろ非効率。
- 指標・高ボラ時に「クレジット込」を当てにした過大ロット→スプレッド拡大で一撃退場。
- EAの資金基準がBalance参照かEquity参照か不一致。パラメータとロジックを要確認。
MT4/MT5での計算ロジックと実務式
新規発注は「Free Margin ≥ 必要証拠金」が条件です。
ここでのFree Marginは多くのブローカーで「Equity(クレジット含む場合あり) − Margin」。
よって、クレジットがEquityに加算される設定なら「発注可能ロット」が直接的に増えます。
一方、リスク許容に基づくロットは次式で保守的に算出するのが実務的です。
- 許容損失額=残高 × リスク%
- ロット=許容損失額 ÷(1pips価値 × 損切りpips)
- 安全係数(例0.8)を掛け、さらに「必要証拠金」の制約を満たすか最終チェック
このやり方なら、クレジット剥奪イベントが発生しても、過大ロットに起因する即死リスクを抑制できます。
ストップアウトとクレジットの関係
ストップアウトは「維持率が閾値を下回る」と発動。
クレジットがEquityに入る口座では、同じ評価損でも維持率が高く保たれやすい一方、クレジットが突然消えると維持率が瞬間的に低下します。
よって、ボーナス消失トリガー(出金・内部振替・ドローダウン閾値)を常に意識し、閾値近辺ではロット縮小やヘッジで防衛する運用が必須です。
結論:どちらが証拠金・ロット計算に反映されるのか
- MT4/MT5の内部計算はEquity・Free Margin・維持率に基づくため、ブローカーがクレジットをEquityに計上していれば「クレジットも反映」され、発注可能ロットと耐性は拡大します。
- ただし、反映仕様と剥奪条件はブローカー次第。A(フル計上)/B(マージン補助のみ)/C(非計上)と幅があり、約款の精読と実機検証が不可欠。
- ロット設計の基準は「残高ベース」が原則。クレジットは「余力を少し増やす補助」と捉え、安全係数をかけるのがプロの実務です。
最後に:実務フローの推奨
- 口座開設直後にクレジット仕様を検証(表示・計算・剥奪条件)。
- 資金管理ルールを残高ベースで固定し、クレジットは無視または安全係数0.5以下で限定的に利用。
- 重要イベント・出金前はポジション軽量化。維持率の急落リスクをゼロに。
- EA/コピー取引はBalance/Equity参照の前提を合わせる(ドキュメントとソース/設定の整合)。
- ボーナス消化狙いの過大ロットを避け、ストップアウト水準+安全域を恒常的に維持。
クレジットは「使い方次第で強力な味方」にも「一瞬で敵」にもなります。
技術的な計上ルールと約款の両面を正しく理解し、残高基準の堅牢なリスク管理で運用することが、長期的な安定収益への最短距離です。
クレジット(ボーナス/与信)は付与・消滅・出金時にどう扱われ、含み損・ヘッジ・ロスカット水準にどんな影響を与えるのか?
クレジット(ボーナス/与信)はこう動く:付与・消滅・出金の実務と、含み損・ヘッジ・強制決済への影響
「残高(Balance)」は実資金、「クレジット(Credit)」はブローカーから付与されるボーナス/与信で、通常は出金不可・条件付きの資金です。
取引プラットフォーム上では有効証拠金(Equity)や余剰証拠金(Free Margin)、証拠金維持率(Margin Level)の計算に反映される場合が多く、裁量やシステムのリスク許容度を大きく左右します。
本稿ではクレジットのライフサイクル(付与・消滅・出金時の扱い)と、含み損・ヘッジ・ストップアウト水準への影響を、実務の視点で具体的に解説します。
付与時に何が起きるか:Equity・証拠金余力・マージンレベル
多くのブローカーでは、クレジットは付与と同時に口座明細の「Credit」欄に計上され、次のような変化が起きます。
- Equity(有効証拠金):ブローカーのルールが「Equityに計上する」型であれば、Equity = Balance + Floating P/L + Credit となり、即座に増加します。
- Free Margin(余剰証拠金):Equityの増加分だけ広がります。これにより新規ポジションの発注余力が拡大します。
- Margin Level(証拠金維持率):Margin Level = Equity / Used Margin × 100(%)。Equityが増えるため、維持率は改善します。
一方で「Equityに計上しない/ドローダウンのクッションに使えない」特殊ルールのブローカーも存在します。
その場合は新規発注時の必要証拠金の一部補助にのみ使われ、維持率やドローダウン耐性は実資金ベースとほぼ変わりません。
利用前に自口座の仕様を必ず確認してください。
消滅・剥奪のトリガー
クレジットは恒久資金ではなく、以下のイベントで一部または全部が消滅することがあります。
- 出金(Withdraw):もっとも一般的なトリガー。比例減額や全消滅のどちらかが多いです。
- 内部振替(Internal Transfer):出金と同様の扱いで比例減額/全消滅となることがあります。
- 有効期限切れ:付与から一定期間で自動消滅。
- 規約違反:裁定/ボーナス濫用/口座間ヘッジなどが疑われた場合の剥奪。
- 口座残高ゼロ化や特定条件の発生:ブローカーによっては「Balanceが0以下になった時点でCredit消滅」等の条項があります。
重要なのは、消滅が「ポジション保有中」に発生し得るという点です。
クレジットがEquityに計上されている口座では、消滅=Equityの即時減少を意味し、維持率が急低下して強制決済が連鎖するリスクがあります。
出金・資金移動時の取り扱いと計算例
出金時の代表的な2パターンとその影響を押さえておきましょう。
比例減額型(プロラタ)
出金額と同割合でクレジットも減額されます。
よく使われる近似式は、
新Credit = 旧Credit ×(出金後Balance ÷ 出金前Balance)
例:出金前Balance 2,000、Credit 2,000。
1,000を出金すると、出金後Balanceは1,000。
新Creditは 2,000 ×(1,000/2,000)= 1,000。
結果、Equityは1,000(Balance)+1,000(Credit)+未実現損益で再計算されます。
全消滅型
少額でも出金した瞬間、Creditが全額消滅。
EquityからCredit分が一気に消えるため、維持率は大きく低下します。
ポジション保有中にこれを行うのは非常に危険です。
いずれの型でも、出金前に「クレジット消滅後の維持率」を事前計算し、Used Margin(必要証拠金)をそれに見合う水準まで減らしてから処理するのが鉄則です。
含み損への影響:どこまでクッションになるのか
クレジットがEquityに計上される口座では、含み損の拡大時にEquityを押し上げるクッションとして機能します。
つまり、同一ロットでも評価損に耐えられる時間(もしくは値幅)が延びます。
ただし誤解してはいけないのは、クレジット自体が「損失を確定的に補填」してくれるわけではない点です。
損切りや強制決済が執行されると、実際に減っていくのはBalanceであり、Creditは規約に応じて残るか消えるかが決まります。
一方、Equityに計上されない型では、含み損のクッション効果は期待できず、あくまで発注に必要な初期証拠金の補助にとどまります。
この違いを理解せずにロットを上げると、想定以上に早いストップアウトに直面します。
ヘッジ時の効き方:必要証拠金と維持戦略
同一銘柄を両建てした場合の必要証拠金はブローカーにより大きく異なります(片側全額+反対側は0、もしくは半額計上など)。
クレジットがEquityに反映される口座では、ヘッジ時の維持率にも直接影響します。
- ヘッジの罠1:クレジット頼みの維持率。クレジットが剥奪されると、Equityが瞬時に減り、ヘッジで低く抑えたはずのUsed Marginに対して維持率が急落し、連鎖ロスカットが起こり得ます。
- ヘッジの罠2:スワップ/スプレッドの摩耗。ロックしたままでも、負のスワップやスプレッド再拡大でEquityはじりじり削られます。クレジットがその摩耗を一時的に覆い隠すため、危険水域に気づくのが遅れがちです。
- 実務対策:クレジットを0としても維持率が基準値(例えば200%など自由に設定)を下回らないロットに抑える。出金や内部振替の前には、ヘッジ片側を軽くする、もしくは合計ロットをリサイズして「クレジット抜き維持率」を再計算する。
ストップアウト水準との相互作用
ストップアウト(強制決済)は、Margin Level(Equity / Used Margin × 100)がブローカー規定の下限(例:20%、50%、100%など)を割った時に発動します。
クレジットがEquityに含まれる場合、同じロットでも維持率低下の速度が緩やかになり、強制決済の発動は後ろ倒しになります。
ただし、次のイベントは例外的に危険です。
- クレジット消滅の瞬間:維持率がドンと下がり、閾値を跨ぐと即座にポジションから切り落とされていきます。
- 全消滅型の出金:わずかな出金でも維持率が致命的に悪化することがあります。
- 段階的ロスカット:1本決済のたびに維持率が再計算され、次々と約定。想定より大きな実損を確定して終了することがあります。
実務シナリオ別の挙動(ケーススタディ)
ケース1:100%ボーナス付与直後にエントリー
入金1,000、クレジット1,000(合計2,000相当のEquity。
Equity計上型)。
レバレッジ1:500、主要通貨で1ロットあたり必要証拠金約200(例)。
5ロット建てるとUsed Marginは約1,000。
維持率は 2,000 / 1,000 × 100 = 200%。
一見余裕があるように見えますが、クレジットが剥奪されるとEquityは1,000に縮小し、維持率は100%まで落下。
ストップアウトが50%のブローカーなら即死は免れても、含み損が少し増えれば一気に危険域です。
ケース2:含み損拡大時のマージンコールと強制決済
Balance 2,000、Credit 2,000、Used Margin 1,500。
含み損が-1,800まで拡大。
Equityは 2,000 + (-1,800) + 2,000 = 2,200。
維持率は 2,200 / 1,500 × 100 ≈ 146%。
まだ耐えているように見えますが、ここでCreditが規約上の理由(期限切れなど)で消滅すると、Equityは400に急減し、維持率は 400 / 1,500 × 100 ≈ 26.7%。
多くのブローカーで即ストップアウトが始まります。
ケース3:利益確定後に部分出金する場合
入金1,000+Credit 1,000でスタートし、取引で+800の実現益。
Balanceは1,800、Creditは1,000のまま。
ここで500を出金。
比例減額型ならCreditは 1,000 ×(1,300/1,800)≒ 722に減少(出金後Balanceは1,300)。
Equityは 1,300 + 722 + 未実現損益。
ポジションを保有したまま出金すると、維持率が想定以上に落ちるため、必ず「出金後のCredit」と「その時点のUsed Margin」から維持率を再計算して、事前にロットを落とすこと。
ケース4:ヘッジロックで耐える戦略の落とし穴
買い1ロットと売り1ロットのロック。
ヘッジ証拠金は片側のみカウント(例:200)。
Balance 1,000、Credit 1,000、Equity 2,000。
維持率は 2,000/200×100=1,000%。
安全そうに見えますが、クレジット全消滅の出金や期限切れが起きれば、Equityは1,000、維持率は500%へ半減。
さらにマイナススワップが積み重なるとBalanceが摩耗し、やがて維持率は規定値近辺まで落ちます。
ロック中はP/Lが固定される一方、コストで削られることを忘れず、ロット縮小や解消プランを持つべきです。
運用ルール:クレジットを前提にしない資金管理
- 「クレジットをゼロと仮定した維持率」を常時計算する。目安式:維持率(クレジット抜き)=(Equity − Credit)/ Used Margin × 100。ここが自分の安全基準(例:200%)を割らないロットに抑える。
- 出金・内部振替の前に、クレジット消滅後の維持率をシミュレーションし、必要なら先にポジション縮小。手続き→決済→再建玉の順ではなく、縮小→手続きの順。
- ヘッジは「クレジット頼みの延命策」にしない。ヘッジ証拠金やスワップの仕様を把握し、解消ラインと時間軸を明確に。
- 規約イベント(期限、規約違反条件、週末/祝日前の変更告知)に敏感になる。ボーナス関連のアナウンスは即チェック。
- ロット計算・ロスカットラインはBalanceベースで引く。EquityやCreditに合わせてロットを拡大するのは最終局面の戦術に限定する。
事前確認チェックリスト
- Equity計上の有無:CreditはEquityに入るか?
入らないか?
- マージン補助の範囲:新規発注時のみか、維持率計算にも反映されるか?
- ストップアウトの閾値:何%で発動し、計算にCreditを含むか?
- 出金時の扱い:比例減額か、全消滅か。内部振替にも適用されるか。
- 期限・剥奪条件:有効期限、放棄条件、規約違反の具体例(口座間ヘッジ、ボーナスアービトラージ等)。
- ヘッジ証拠金の計算:片側0、半額、同額のいずれか。銘柄ごとの差はあるか。
- スワップ・証拠金変更:イベント時や週末の一時的な証拠金引き上げ、スワップの臨時変更の予定有無。
まとめ:クレジットは「増える資金」ではなく「変動する条件」
クレジット(ボーナス/与信)は、付与時には余力と維持率を押し上げ、含み損に対してクッションとして機能する一方、出金・内部振替・期限や規約イベントで突然消滅し得る「条件付きの証拠金」です。
とくにヘッジや高ロット運用でのクレジット依存は、消滅トリガー一発で維持率が崖落ちし、想定外のストップアウトを招きます。
実務では、常に「クレジット0でも安全か?」を基準にポジションを組み、出金や資金移動の前には維持率を再計算してリサイズ。
ヘッジは延命ではなくコストと解消プランを伴う戦術として扱う。
規約・仕様の差はブローカーごとに大きいため、実口座で小ロット検証し、出金テストまで含む「フル・ドレス・リハーサル」を済ませてから本格運用に移るのが安全策です。
残高とクレジットの比率別に、適切なロットサイズ・損失許容・最大ドローダウンはどう設計すべきか?
残高×クレジット比率で決めるロットサイズ・損失許容・最大ドローダウン設計の実務テンプレート
同じ口座残高でも、クレジット(ボーナス/与信)の有無や比率によって、適正ロットやリスク許容は大きく変わります。
特にMT4/MT5ではクレジットがエクイティや証拠金余力に反映されるケースが多く、実力以上のロットを張りやすい構造になっているため、比率に応じた明確なルールが不可欠です。
ここでは、残高とクレジットの比率別に「ロットサイズ」「1回あたりの損失許容」「最大ドローダウン」をどう設計するかを、実務でそのまま使える形で体系化します。
まず押さえる基本概念
- 残高(Balance):確定損益を反映した口座の元本。ここを「守る資本」とみなす。
- クレジット(Credit):ブローカーが付与する与信/ボーナス。消滅条件があるため「変動する条件」。
- 有効証拠金(Equity):残高+含み損益+クレジット。発注・維持に関わる即戦力。
- 使用証拠金・余剰証拠金・マージンレベル:ロットを増やすほど消費。クレジットの扱いはブローカー仕様依存。
設計の原則は「残高を基準資本(守る資本)に、クレジットはドローダウンクッション(緊急用)として扱う」ことです。
クレジットをロット計算にフル反映するのは事故の温床になります。
3つの設計原則(骨格)
1. ロットは「保護対象資本×一定リスク」で一貫して決める
許容損失額 = 基準資本 × リスク%(1回のトレード)
ロット = 許容損失額 ÷(ストップ幅pips × 1pip価値)
基準資本は「残高+(クレジットの一部)」で定義しますが、クレジット比率が高いほど加算比率を小さくします。
2. クレジットは「使ってもよいが当てにしない」
クレジットは耐える力を高める補助としては有効。
ただしロット計算の土台には基本的に載せない。
載せる場合も一部のみ(最大でも50%)に制限します。
3. 最大ドローダウンは「残高基準」と「エクイティ基準」の二重リミット
- 残高最大ドローダウン(Hard):資産保全の最終防衛線。超えたら運用停止・ロット再定義。
- エクイティ・トレーリング(Soft):日次/週次の損失上限や段階的リスク縮小で早めに減速。
ロット計算の標準式(実務)
手順はシンプルです。
- 基準資本(Base)を決める:Base = 残高 + w × クレジット(wは0~0.5の重み)
- 1回あたりのリスク%(R)を、比率テーブルで決める
- 許容損失額(A)= Base × R
- ロット = A ÷(ストップ幅pips × 1pip価値)
参考:USDJPYを円口座で取引する場合、1ロット(100,000通貨)の1pip価値はおおよそ1,000円。
0.1ロットで約100円、0.01ロットで約10円。
ストップ幅が30pipsなら、0.01ロットの損失は約300円。
これを基準に逆算すれば、適正ロットがすぐ出ます。
比率マップ:クレジット/残高(C/B)で決める推奨パラメータ
クレジット比率C/Bに応じて「w(クレジット加算率)」「1回リスク%」「日次損失上限」「最大DD」を段階設計します。
A. C/B=0%(クレジットなし)
- w=0(Base=残高)
- 1回リスクR=0.5~1.0%
- 日次損失上限=2.0~3.0%
- 最大DD(残高基準)=10~15%
- 運用メモ:標準的なリスクレンジ。勝率や期待値に応じてRを0.75%前後に集約すると安定。
B. C/B=1~50%
- w=0~0.25(Base=残高+0~25%×クレジット)
- 1回リスクR=0.4~0.8%
- 日次損失上限=1.8~2.5%
- 最大DD(残高基準)=10~12%(エクイティ基準=15~18%)
- 運用メモ:クレジットは最大25%だけロット計算に乗せる。ドローダウン初期でRを半減する制御を設定。
C. C/B=51~100%
- w=0~0.3(Base=残高+最大30%×クレジット)
- 1回リスクR=0.3~0.6%
- 日次損失上限=1.5~2.0%
- 最大DD(残高基準)=8~10%(エクイティ基準=20~25%)
- 運用メモ:与信依存が進む帯。ロット増加は厳禁。日次連敗で即Rを0.3%へ落とすルールを事前化。
D. C/B=101~200%
- w=0~0.2(Base=残高+最大20%×クレジット)
- 1回リスクR=0.2~0.4%
- 日次損失上限=1.2~1.8%
- 最大DD(残高基準)=6~8%(エクイティ基準=25~30%)
- 運用メモ:クレジットのフル計上は事故源。ヘッジやナンピンを使う場合はロットをさらに1/2へ。
E. C/B>200%
- w=0(Base=残高のみ)
- 1回リスクR=0.1~0.25%
- 日次損失上限=1.0~1.2%
- 最大DD(残高基準)=5~6%(エクイティ基準=30%前後)
- 運用メモ:クレジットは完全にクッション扱い。ロット計算から除外。想定外の急変動対策に温存。
数値例:同じ残高でも比率でこう変わる
前提:残高=100,000円、ストップ=30pips、銘柄=USDJPY、1ロット1pip≒1,000円。
1) C/B=0%(クレジットなし)
- Base=100,000円、R=0.8% → A=800円
- ロット=800 ÷(30×1,000)≒0.026 → 0.02ロットに丸め
2) C/B=50%(クレジット50,000円)
- w=0.25 → Base=100,000+12,500=112,500円
- R=0.6% → A=675円
- ロット=675 ÷(30×1,000)≒0.0225 → 0.02ロット
- メモ:与信があってもロットは微増か現状維持。耐久力だけ上がる設計。
3) C/B=100%(クレジット100,000円)
- w=0.3 → Base=100,000+30,000=130,000円
- R=0.5% → A=650円
- ロット=650 ÷(30×1,000)≒0.0217 → 0.02ロット
- メモ:クレジット倍増でもロットは据え置き。ドローダウンの底堅さが主効果。
4) C/B=200%(クレジット200,000円)
- w=0 → Base=100,000円
- R=0.25% → A=250円
- ロット=250 ÷(30×1,000)≒0.0083 → 0.01ロット
- メモ:過剰与信ゾーンはむしろリスクを下げる。守りに徹する。
最大ドローダウン設計:二重リミットと段階的リスク低下
設計のキモは「早めに火力を落とす」こと。
推奨は以下の二段構えです。
ハードリミット(残高基準)
- C/B=0~50%:残高最大DD=12%(達したら運用停止、復帰は残高が-8%以内に戻ってから)
- C/B=51~100%:残高最大DD=10%
- C/B>100%:残高最大DD=6~8%
ソフトリミット(エクイティ基準・トレーリング)
- リカバリー係数を意識:月間の期待利益%よりDD%が大きくならない設計
- 前日ピークエクイティから-2%でRを半減、-3%で当日停止
- 週次ベースで-4~6%到達で翌週まで待機(ニュース・ボラチェック)
ロット縮小のトリガー例
- 連続損失3回でR×0.5、連続損失4回で当日停止
- 含み損がBaseの2%超えで新規エントリー禁止、決済専念
- エクイティが「残高-最大DD×残高」を割り込む前に、全ポジションのストップを集約して損失確定
日次・週次リスク制限の目安
- C/B=0~50%:日次上限1.8~2.5%、週次上限4~6%
- C/B=51~100%:日次上限1.5~2.0%、週次上限3~5%
- C/B>100%:日次上限1.0~1.5%、週次上限2.5~4%
いずれも「上限到達=終了」を徹底。
取り返そうとする増し玉は「最大DDを短期で達成」させる最短ルートです。
ポジション管理:分割・逃げ・ヘッジの使い分け
- 分割エントリー:1回の想定ロットを2~3分割。初弾が踏まれたら追加は1/2だけ。合計リスクはR以内に。
- ブレイクイーブン移動:+1R到達で半分利確+残り建値。連敗期のエクイティ改善に効く。
- ヘッジ:C/Bが高い時ほど乱用は禁物。必要証拠金が増え、マージンレベル低下→ストップアウトに近づく。
- ナンピン:Rの範囲で設計された「計画的分割」と、負けを追うナンピンは別物。後者は禁止。
ボラティリティとニュースに応じたRの可変ルール
- ATR拡大(平常時の1.5倍超)/重要指標前後:Rを0.5×へ。ストップは広く、ロットは小さく。
- 閑散・スプレッド拡大:エントリー回数を半減。誤発注・スリッページでR超過が起きやすい。
- イベントドリブン(政策金利・要人発言):発表前は建玉を軽く、クレジットに頼らず一時退避。
運用フロー(毎日・毎週のルーティン)
- 開始前:残高・クレジット・エクイティを記録し、C/Bと当日のR・日次上限を確定
- 中盤チェック:エクイティドローダウンが-1.5%/-2%/-3%のどこにあるかを把握、段階制御
- 終了時:損益・最大含み損・実効Rを記録、次営業日のRを微調整(増やすのではなく戻す)
- 週末:最大DD・勝率・平均RRをレビュー。C/Bの変化でwとRを再設定
比率別の「やってはいけない」典型
- C/B>100%で、クレジットをフルにロット計算へ反映
- 日次上限到達後の取り返しトレード(マーチン化)
- ヘッジで証拠金を圧迫し、ストップアウト水準に近づく
- 出金や内部振替でクレジット消滅条件を踏み、耐久力が突然低下
簡易チェックリスト(実装テンプレ)
- 今日のC/B=?
→ 帯はA~Eのどれ?
- w=?、Base=残高+w×クレジット
- R=?
%、日次上限=?
%、週次上限=?
%
- 銘柄の1pip価値=?、ストップ幅=?
pips → ロット=?
- 連続損失時の段階ルール(R半減・停止トリガー)は設定済み?
- ハード最大DD(残高基準)=?
% → 到達時の停止条件は明文化済み?
まとめ:比率で攻守を切り替え、クレジットは「耐久力」として使う
残高とクレジットの比率が高いほど、ロットは小さく、最大DDは浅く、日次上限は厳しく設計します。
ロット計算の基礎にクレジットを過度に含めないことが、長期の資産曲線を右肩上がりに保つ最短経路です。
実務では「Base=残高+w×クレジット」「Rは比率帯で範囲固定」「二重DDリミット+段階的R縮小」という3点セットを毎日回すだけで、過ちの大半を未然に防げます。
最後にもう一度。
クレジットは武器ではなく盾。
盾を当てにして前に出るのではなく、背中を守るために使う。
これが比率時代のリスク設計のコア思想です。
最後に
フル計上型では、残高1,000USD+クレジット1,000USD=Equity2,000USD。
未決済損益0ならFree Marginも2,000USD。
証拠金余力が倍化し発注可能ロットが拡大。
レバレッジ1:500想定。
ドローダウンのクッション効果もある一方、出金等で剥奪時は維持率急落に注意。
ボーナス条件とロスカット水準を要確認。


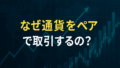
コメント